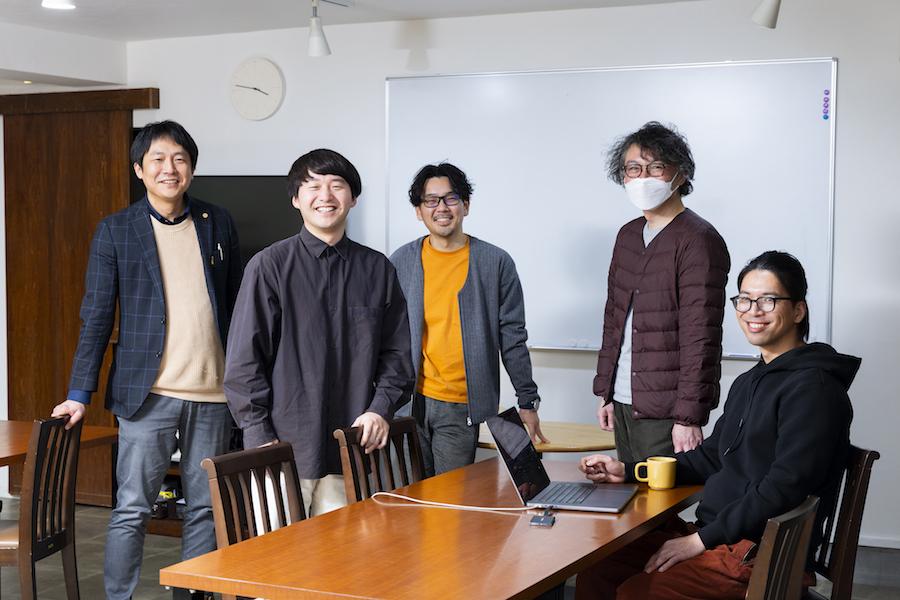
現在、全道の市町村で「地域おこし協力隊」の方たちがさまざまなジャンルで活躍。くらしごとでもたくさんの協力隊の方たちを取材してきました。協力隊という同じ制度を利用していても、各自治体で協力隊への関わり方や採用の目的、活動内容などは大きく異なります。今回は、長沼町で活動中の協力隊メンバーにお話を伺うとともに、協力隊OBを中心に任期を終えたあとのことを考えた仕組み作りをスタートさせるということで、その内容についてお話を聞いてきました。
神奈川出身の現役協力隊。移住定住担当と観光担当の2人
 長沼町の現役協力隊員のお二人。左が移住定住担当の江藤さん、右が観光担当の金山さん
長沼町の現役協力隊員のお二人。左が移住定住担当の江藤さん、右が観光担当の金山さん
長沼町の中心部にあるコワーキングスペース「ながぬまホワイトベース」。地元で起業している人はもちろん、地域おこし協力隊のメンバーやOBもここで仕事をしています。今回はお話を伺う現役協力隊は4人。まずは2023年11月から隊員として赴任した江藤誠洋さんと、2024年4月に赴任した金山真大さんに登場してもらいます。
2人とも神奈川県出身。同じ時に長沼町の地域おこし協力隊に応募しましたが、前職の兼ね合いなどもあり赴任時期が少し異なるそう。
現在、江藤さんは移住定住担当として移住フェアなどに出たり、移住を考えている方たちの相談に応じたり、SNSで町の情報発信を行ったりしています。一方、金山さんは観光担当。観光協会の仕事や町で行うイベントの裏方仕事などに携わっています。
 移住定住担当の協力隊・江藤さん。SNSでの発信が人気で、DMでの移住相談数がとても増えたそう
移住定住担当の協力隊・江藤さん。SNSでの発信が人気で、DMでの移住相談数がとても増えたそう
2人が長沼町の地域おこし協力隊に応募しようと思ったきっかけを伺うと、まずは江藤さんが「僕はもともと住宅メーカーで設計の仕事をしていました。子どものころ、長野に住んでいたことがあって、都会より少し田舎のほうがしっくりくると思っていて、いつか移住したいと考えていました。妻が網走出身ということもあり、長野か北海道を移住先の候補に考えていて、説明会で話を聞いて長沼に来ました」と教えてくれました。
 観光担当の協力隊・金山さん。前職は旅行代理店の営業マン
観光担当の協力隊・金山さん。前職は旅行代理店の営業マン
旅行代理店で法人営業の仕事をしていた金山さんは、「3年前から北海道でゲストハウスをやりたいと考えていて、有楽町にあるどさんこ交流テラスで長沼町を紹介されたのが最初のきっかけです」といいます。長沼町に決めた理由については4つあったそうで、「まず新千歳空港が近いこと、次に野菜がうまい、それから協力隊の募集が5人採用ということで自分的にはその人数がちょうどよかったのと、前職の経験を生かせる観光系ミッションだったこと。そして、高田さんの存在」と教えてくれました。隣で聞いていた江藤さんも「高田さんの存在は大きかったよね」と同意。
 長沼町役場の高田和孝さん。協力隊員から厚く信頼される存在です
長沼町役場の高田和孝さん。協力隊員から厚く信頼される存在です
その高田さんとは、長沼町政策推進課企画政策係の高田和孝さんのこと。地域おこし協力隊の担当で、隊員たちのまとめ役であり、相談役でもあります。「とにかく話をじっくり聞いてくれるんです」と金山さん。この高田さんの人柄も長沼町を選ぶ決め手になったと話します。「僕が話を聞いたときは、高田さんともうひとり、役場の方がいらしたんですけど、2人とも長沼のことが好きで、長沼での暮らしを楽しんでいるのが話をしているとすごく伝わってきて、自分が暮らしている町をこんなふうに語れるっていいなと思ったんです」と江藤さん。
長沼町での暮らしを満喫。協力隊の活動の傍ら、自身のやりたいことも形にしていく

長沼に移住してからのことを伺うと、江藤さんは「移住関連のイベントに出ることが多くて、結構出張に行くのですが、長沼の町での暮らし自体は想像していた通りというか、すごく満足しています。週末には温泉に行ったり、冬はスキーを楽しんだりして楽しんでいます。地域の方たちとの距離感もちょうど良くて」と笑顔。まちづくりや町の活性化に興味関心のある町民が多く、「協力隊の活動もしやすい」と感じていると言います。また、長沼にはおしゃれなカフェがたくさんありますが、奥さんも地元の人と交流したいとカフェで月に数日働いているそう。夫婦で町の暮らし、仕事を楽しんでいるのが伝わります。
金山さんは長沼のことを「田舎すぎず、都会すぎず、暮らしやすい町。町の人たちも移住者に対してやさしいです」と話します。協力隊の活動の傍らゲストハウスの運営をする許可を事前にもらっていた金山さん、2024年の秋に民泊の許可を取り、年明け1月から「旅人の宿人(やんと)」という名前で本格的に営業をスタート。長沼に来る際、江藤さんから「こういうところがあるよ」と物件を紹介してもらい、とんとん拍子で話が進んだそうです。現在、協力隊の仕事の合間を縫ってゲストハウスの仕事をしており、「勤務時間に関しても臨機応変に対応してくれるのでありがたい。意見を尊重し、いい意味で自由にやらせてくれるところに町の大らかさを感じます」と語ってくれました。
これからのことを尋ねると、江藤さんは「協力隊としては、ほかの自治体の移住コーディネーターの方たちとも繋がりを持ち、移住定住に関することを吸収したいと考えています。あとは移住相談、お試し住宅の受け入れの件数を伸ばしたいですね。それと、空き家の掘り起こしを強化したいと思っています。移住相談で興味を持ってもらっても住む場所がないと移住が成立しないので」と話します。役場の高田さんは「江藤さんは移住定住担当として大活躍してくれて、彼が来てから移住の相談がものすごく増えたんですよ」と絶賛。金山さんも「相談者の方にすごく丁寧に対応していて、第2の高田さん感ありますよ」と笑います。
昨年、地域の人達との交流の場として「協力隊居酒屋」を開催。協力隊メンバーが力を合わせて準備、実施しました。今年はそこに移住者や移住を検討している人も集まれるようにしたいと構想しているそう。
江藤さんは「個人的には住宅の設計の仕事をしていたので、その経験を生かしたこともしたいと思っています。長沼の雰囲気や暮らしの道具をうまく取り入れた空間づくりを施したコンセプト型の1棟貸しの宿をやってみたいと考えて、少しずつ動き始めています」と夢も教えてくれました。
金山さんが今年やりたいことは、旅行会社を作ることだそう。「アクティビティを取り入れたツアーを組む着地型の旅行会社を長沼で興したいと考えています」と話します。先々のことを尋ねると、任期が終わったあとも長沼を拠点に、ゲストハウスをやりながら、旅行の添乗員をやれたらと考えているそうです。
自身が掲げたミッションを形にして事業を推進。外部からも高く評価
さて次に、一昨年(2023年)の11月からフリーミッション型の協力隊として長沼で活躍している徳留正也さんと、昨年10月に同じくフリーミッション型の地域おこし協力隊として赴任した曹 冠宇(そう かんう)さん、協力隊の先輩と新人さんに登場してもらいます。
 フリーミッション型の協力隊・徳留さん。昨年、フリーランスのお仕事サイトで表彰された際の楯を見せてくれました
フリーミッション型の協力隊・徳留さん。昨年、フリーランスのお仕事サイトで表彰された際の楯を見せてくれました
徳留さんは昨年、協力隊として赴任して数か月のとき、くらしごとにも登場。その際は、「テレワークの推進」を掲げて活動を始めようとしていたところでした。「あの後、在宅ワークセミナーなどを町民向けに開催するなどの活動を行いました。また、僕はもともと町から許可をもらって、営業代行などテレワークの仕事を行っているのですが、今年、クラウドソーシングのプラットフォームから賞もいただいたんです」とニッコリ。代行業を通じてあらゆる企業のサポートを行いながら、協力隊として地域と連携し、移住という経験を活かして地方における新しい働き方の可能性を開拓したと評価されたそう。

昨年会ったときに比べ、徳留さんの雰囲気が随分と柔らかくなった印象を受けましたが、「1年経って、町の人ともイベントなどを通じて交流する機会が増え、自分の中にあった警戒心のようなものが取れたのかもしれません。町の人は皆さん親切で、移住者に対して温かく接してくれるんですよね」と話します。また、夏は涼しく快適で、冬も今年は雪が少なくて過ごしやすかったそう。生活のリズムも整い、「ストレスが減った状態で仕事ができているというのも大きいかもしれませんね」と自身で分析。気持ち的にも余裕のある暮らしを送っているのが伝わってきます。そして、調理師の免許を持っている徳留さん、4月以降は食品加工のことなどもチャレンジしてみたいと話してくれました。
3年の任期の間に、夢を形にするための準備ができるのは魅力

一方、曹さんは中国の大連出身。10年ほど前に来日して東京や大阪で映像カメラマンとして活動し、以前から憧れを持っていたという北海道へ。現在は、協力隊として町のイベントの撮影などをする傍ら、町を舞台にしたドラマを撮っているそう。「町民の方たちにも出演してもらい、観光客の人たちにこのドラマを見て長沼の町を回遊してもらえるような仕掛けをしたいと考えています」と流ちょうな日本語で話します。映像の公開の仕方も工夫し、面白いものにしたいと意気込みます。気になるこのドラマ、6月ごろに完成予定なのだそう。
徳留さんはすでに協力隊の活動とは別に自身で事業を行っていますが、曹さんもゆくゆくは映像制作の会社を長沼で立ち上げたいと考えています。「協力隊のフリーミッションのシステムはとてもいいと思います。3年かけて町や町の人と繋がりを深めながら、自分のやりたいことの準備ができるのはとても魅力的です」と熱く語ります。ちなみにどのような映像作品を撮りたいと考えているか尋ねると、「長沼もそうですが、今ある各観光地のPR動画はワンパターンな印象。そうじゃない見せ方、切り取り方で町をPRできるようなものを作りたいと考えています」と教えてくれました。
曹さんから見た長沼町の人の印象は、「日本語をしゃべっている外国人みたいな感じ」。これまで暮らした本州で出会った人たちと違い、長沼の人はみんな気さくで友好的だということなのだそう。「僕が地域おこし協力隊だと広報誌などで知った町の人が、どんどん声をかけてくれるんです。日本に来てこういう経験は初めてだったから、とても新鮮です」と話します。
奥さんが妊娠中という曹さん。「長沼は、大阪や東京といった都会と違って夜も静かだし、暮らしやすい。町も人も大らかで、子育てするのにもいい環境だろうなと思っています」と最後に笑顔で話してくれました。
協力隊を終えたあとのことを現役のうちから一緒に考え、サポート

最後に登場するのは、この春に、今回紹介した4人の協力隊と一緒に一般社団法人「まおいのはこ」を立ち上げた代表の坂本一志さんです。坂本さんは協力隊OBで、昨年、徳留さんと一緒にくらしごとでも取材をさせてもらいました。
協力隊を終えたあと、行政書士として町内で活動している坂本さんは、町内の仲間で立ち上げた有志の非営利会社「一般社団法人ながぬま」の理事も務めています。昨年はこれまで培った人脈や経験を生かし、この団体を通して地域おこし協力隊の研修や補助金活用等のサポートを行ってきました。
今回、まおいのはこを立ち上げた理由について、「一般社団法人ながぬまは元々、まちづくりや子どもの体験活動といった様々な分野に興味を持つ仲間の集まりでした。一方、今回設立したまおいのはこは、協力隊自らが参加する形で、協力隊に特化したサポートを行います。現役の協力隊メンバーに入ってもらい、彼らが次にやってくる協力隊の力になってもらい、またその次に...という感じで、協力隊のOBと現役が繋がりを切れ目なく持てる仕組みを作りたいと考えています」と坂本さんは話します。
こう考えるようになったのには、過去の失敗があるからと坂本さん。コロナ禍ということもありましたが、2021年に一度協力隊の繋がりが途絶えてしまったことがあったそう。「協力隊の期間中に町を好きになってもらい、任期を終えたあと、いかに町に残ってもらうかが重要。そのためにはサポートしてくれる人や組織の存在が欠かせないと思うんです」
さらに、「僕はもともと江別市の職員で、そのあとに地域おこし協力隊で長沼に来たのですが、元公務員から言わせると、公務員の立場と経験で協力隊を終えたあとの皆さんを食べていけるようにサポートするのは難しい。でも、民間ならそういうサポートをする組織なら作れる。協力隊のみんなが活動している間に、地域との関係性を深め、残って起業するなり、何か新しいことを始めたりするための助走期間のお手伝いはできると思うんです。協力隊を終えたあとの出口戦略としての支援組織ですね」と話します。
「まおいのはこ」と名付けた理由を「現役の協力隊のみんなの巣箱のようなものになったらという思いと、あとIT用語のサンドボックス(通常利用の領域から隔離・保護された仮想的空間)のようなイメージから、『はこ』と付けました」と坂本さん。「まおい」とは、長沼町の緩やかな丘陵地帯の呼び名。現役協力隊のみんなに、協力隊でいる間に長沼でやりたいこと、チャレンジしたいことを「まおいのはこ」を使ってやってみてほしいといいます。
長沼の協力隊の活動内容に、フリーミッション型、ミッション型問わず全職種共通で年に10回ほどある町内各種イベントへの参画という項目があります。これがあることで、町の人たちとも自然と交流を深めていくことができます。でも、これだけだとただ仲良くなって終わりですが、協力隊を終えたあとにどうしたいか、何をしたいかを考えたとき、サポートしてくれる「まおいのはこ」のような組織があると、任期後も仲良くなった町の人たちと交流を続けながら、自分の夢ややりたいことを実現させることができます。今回お話を伺った現役4人の協力隊もそれぞれに具体的なビジョンを掲げていましたし、徳留さんや金山さんのようにすでにやりたいことを形にしている人もいます。そうした先輩協力隊がいて、彼らと繋がれる場所もあり、任期終了後も町で快適に暮らし、仕事ができる。このように任期後のビジョンを描きやすいのは大きな魅力だなと感じました。




























