
木材産業の世界では、業務内容によってそれぞれ川上・川中・川下と分類されることがあります。川上は、木を生産する林業そのものを指します。一方川下は、伐り出された木を使う建設業者や木工業者、そして私たち消費者になります。そして、今回おじゃました新得町にある関木材工業は川中の部分にあたる木材加工を担っている会社です。同社の4代目である山内ゆかりさんに会社のことを伺ったほか、九州から移住し、30年働いているベテランの社員・福田勇さんにも話を伺いました。
石材屋、移動製材を経て、カラマツの梱包材を作る製材工場を設立
国道38号沿い、狩勝峠から15キロほどのところに「関木材工業」があります。広い敷地内には、たくさんの丸太や製材された木材がいたるところに置かれ、製材作業をしている工場からは木の香りが漂ってきます。
「皆さん『木のいい香りがしますね』とおっしゃるんですけど、毎日のようにここにいると、もう分からなくなって」と、代表取締役社長の山内ゆかりさんは笑います。山内さんは同社の4代目。平成28(2016)年に社長に就任しました。
 株式会社関木材工業、代表取締役社長の山内ゆかりさん
株式会社関木材工業、代表取締役社長の山内ゆかりさん
「もともとは、曾祖父にあたる関新太郎が新得で石材屋を営んでいました。狩勝峠から切り出した花崗岩(かこうがん)は、駅のホームなど鉄道建設に用いられたほか、釧路の幣舞橋をはじめ、全道の大きな橋や神社の鳥居に用いられたそうです。その後、息子である関一郎、私の祖父が移動製材業を始めたと聞いています」
鉄道の枕木や農家の納屋などを作る際、製材機械(丸のこ)を現場に運び、近くから伐り出された丸太をその場で製材していたそう。「丸太を工場に運んで製材するよりも、当時はそのほうが効率も良かったのでしょうね」と山内さん。
移動製材の仕事が定着し、昭和38(1963)年、現在の場所とは異なりますが、新得町内に製材工場を建てます。これが関木材工業の創業となります。最初は家族経営だったそうで、「私が赤ちゃんだったころ、母は私をおぶって製材をしていたらしいですよ(笑)」と山内さん。
「私の父、関道孝が2代目となり、昭和56(1981)年に今のこの場所に工場を移しました。家族や親族が総出で仕事をしていて、私も小学生のときは夏休みなどの長期休みになると、板状にカットされた木をスズランテープのようなものでまとめて縛る作業などを手伝いましたね」
当時は、道産カラマツの専門工場として、車の部品を運ぶ物流材「梱包材」を主に製材していたそう。
「道産のカラマツは強度が強いので、家を建てる建築材として用いられていました。ただ、太くて節が少ないものしか使うことができなかったため、カラマツの間伐材の小径木をいかに活用するか考え、父や周りの同業者の方たちはそれを物流材や梱包材として用いることにしました」
自動車メーカーが海外で組み立てを行うために部品を船で運ぶ際、このカラマツの梱包材や木枠がとても重宝されたそう。これらは苫小牧港などの港から本州の自動車メーカーの工場へ運ばれるため、太平洋側の港へ輸送しやすいという立地条件もあり、業績は伸びていきます。さらに先見の明があった2代目の道孝さんは、敷地内に新しい工場を次々建て、他社よりもいち早く新しい機械や乾燥機を導入していきます。
日本初のトドマツの2×4材工場を立ち上げるものの、2代目に病が発覚
「私自身は高校を卒業後は新得を離れて帯広で就職し、そのあと、通関士だった夫と結婚して、広尾や苫小牧で暮らしていました。ちょうど平成7(1995)年に父が屈足(くったり)に新しい工場を立ち上げることになり、そこを夫に手伝ってほしいと声がかかり、家族で新得へ移ることになりました」
ところが、新得へ引っ越したタイミングで父の道孝さんが体調を崩します。大きな病院で検査してもらったところ、脳腫瘍があると分かります。
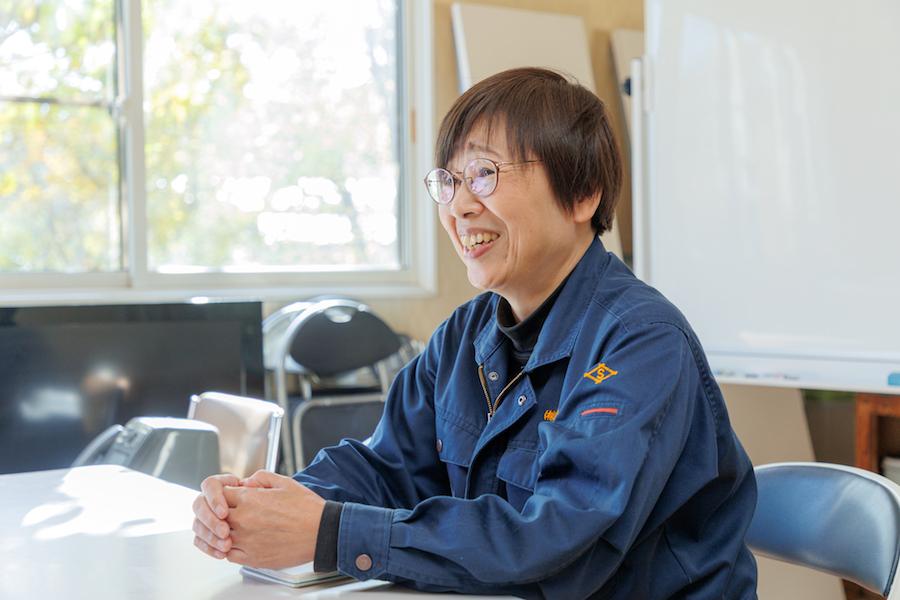
「平成7年の12月に新しい工場が立ち上がったのですが、父はすぐに闘病生活に入ってしまい、翌年の12月に亡くなってしまいました。何の引き継ぎもないまま、新しい工場を任された夫はとても苦労したと思います。私自身も、事務所の手伝いをしながら母と交代で父の看病にあたり、あの1年間はとにかく忙しかったという記憶しかありませんね」
父の道孝さんが屈足に新たに作った工場は、日本初の国産材による2×4(ツーバイフォー)建材の工場でした。トドマツの使い方を模索する中で2×4材の製材にチャレンジしようということで、カナダから輸入した機械を導入し、工場は稼働を始めます。
「でも結局、父は病院に入っていて何もできる状態ではなく、本当に手探りで工場を稼働させていたようです。当時専務だった父の弟がいてくれたおかげで何とかやってこられたという感じでした」
3代目の叔父の跡を受け、4代目に就任。父が残した工場に新しいラインを設置
3代目には専務だった父の弟・関孝和さんが就任します。子育て中だった山内さんもパート社員として事務方の手伝いを続け、翌年には正社員として事務所内の仕事をこなしてきました。
そして、平成28(2016)年に山内さんが4代目社長に就任し、3代目の孝和さんは代表取締役会長に。
「ずっと現会長のそばで仕事は見てきて、経理もやっていたので、会社の中のことはよく分かっていたのですが、いわゆる外回りはしたことがなかったので、就任してすぐはとにかく取引先の方たちのところへの挨拶回りをしながら、経理も見るという感じで慌ただしかったですね」
社長になったとき、山内さんは屈足にある工場を直し、新しいラインを作りたいと考えていました。
「こちら側の工場(事務所がある敷地内の工場)は、受注生産のカラマツ専門で黒字が続いていましたが、父が亡くなる前に建てた屈足のトドマツの2×4材の工場は採算が取れるか取れないかという状況でなんとかやってきました。2×4材以外に梱包材に取り組んでみたりもしましたが、そのときはなかなか思った通りにはいかず...。さらに工場ができたときに入れたカナダの機械が古くなり、そのメーカーもなくなってしまいメンテナンスができなくなっていたため、それなら新しい機械を入れて新しいラインを作ったほうがいいと判断しました」
屈足工場ではトドマツを使った梱包材やパレット材の製材を中心に方向転換。それが軌道に乗ると、トドマツの2×4材も5年前から本格的に再開しました。ちょうど国産材への切り替えが進んでいた頃だったため、その波にも乗った形になりました。
「2×4材に関しては細々とでも続け、その技術を継承していかなければと考えてはいたので、完全に辞めてはいなかったんです。また、新しいラインを作ったときに、一部無人化も試してみました。どの業界でも人手不足といわれる中で、私たちも今後省人化していくことが課題となっています。トドマツのほうの一部無人化は今も続けていて、今後はこちらの工場のほうでも取り入れていければと考えています」
森林の循環サイクルを守るためにも付加価値をつけ、次世代へ繋ぎたい
「この仕事をしていると、世界と繋がっているなぁとよく実感するんです」と山内さん。梱包材は輸出に大きく関わっているため、世の中の動向に左右されることがしばしば。リーマンショックのときは2カ月間工場の稼働をストップしたそう。その一方で、コロナ禍のときは一度海外へ出たスチール等のリターナブルラックが戻ってこないため、木材の梱包材やパレットの需要が一気に高まったと話します。
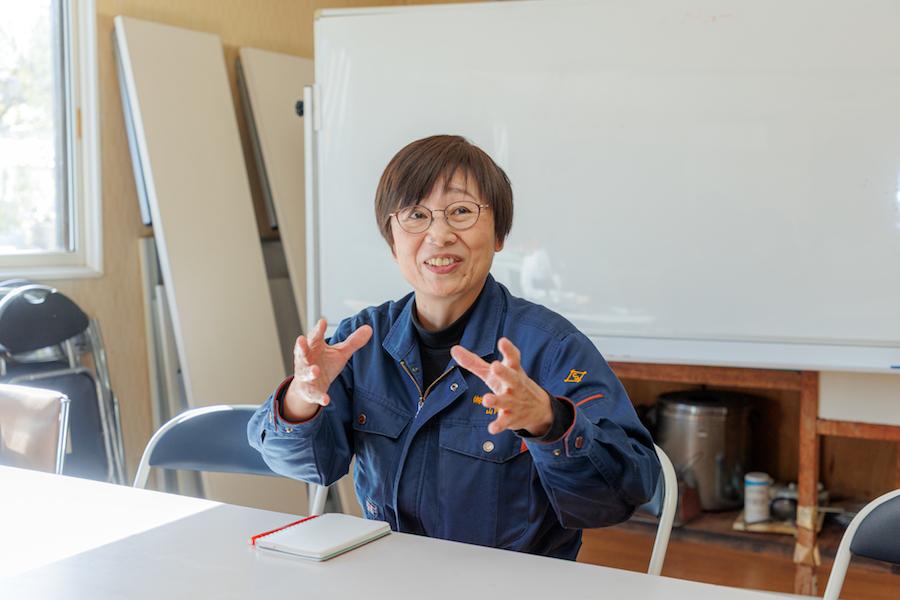
「梱包材、パレット材は受注生産ですべて対応しています。お客さまの希望に応じて自在なサイズに対応できるのが道産カラマツの強みであり、当社の強みでもあると思います。基本的に木の余剰在庫を持たないで済んでいるのは、受注生産のおかげなんです」
十勝を中心に、富良野方面や根釧地区からも原料となる丸太を仕入れているという同社。「安定的に木材を供給してもらえるのはありがたい」と山内さんは話します。
「森林は温暖化防止などに大切なもの。持続可能な森林の循環利用が大事で、そのためには、木を伐って、それを無駄なく使って、そしてまた植えるというサイクルが大切。北海道のカラマツ、トドマツもより計画的に植え、伐採していかなければ、なかなか循環していかないのかなと感じています。北海道の森林には、本州にはない特徴があります。それぞれの地域性に合った森林資源の循環活用を目指していけたらと思いますね。さらに、育てた木に価値を付け、私たち川中の人間もいかに木材製品に付加価値を付けて市場に出していくかも課題です。結果として付加価値を付けることが、山へ還元されると考えています。そして私たちの製材技術も、林業の方たちの山の管理も、今やるべきことをやらないと、次の世代へバトンを渡せないと感じています」
最後に敷地内の工場を案内してもらうことに。機械を使って丸太の皮をむき、面をつけ、必要な厚さや長さにカットしていく様子を順に見せてもらいました。
「仕入れた木は梱包材やパレット材、あるいは2×4材に製材しますが、製品として使えない部分のものはすべてチップにし、パルプに。さらに副材のおがくずなどは牧場の牛の寝床に用い、どの木も無駄なく全て使い切ります」
長年、この業界に携わってきた山内さんは、「道産カラマツの梱包材は日本経済の土台、根幹を支えている商材だと思う」と話します。「この梱包材は、これからも絶対に必要なもの。私たちがそういうものを製造しているということを少しでも多くの人に知ってもらえたら」と最後に語ってくれました。
移住から30年。長く働き続けられたのは、居心地がいい職場環境だから
次に、本社工場から車で10分ほど離れたところにある屈足工場へ向かいました。ここでは、入社30年というベテランの工場スタッフの福田勇さんにお話を伺いました。
長崎県出身の福田さんは、ちょうど30年前に芽室町へ家族と移住。お子さんの生活環境を変えたい、寒くて広いところへ行ってみたいという思いから、縁もゆかりもなかった北海道へ移住を決めたそう。
 屈足工場で勤務する福田勇さん
屈足工場で勤務する福田勇さん
「移住ツアーみたいなのがあって、道内のいろいろなところを見たんですけど、十勝にバスから降り立ったときの空気がカラッとしていてよかったんですよね」
当時、移住者を積極的に受け入れていた芽室町の上美生(かみびせい)というエリアに移り住み、仕事を探し始めますが、なかなかピンとくるものがなかったそう。
「それまでずっと営業の仕事をしていたんです。こっちに来たとき、ちょっと違う仕事がしてみたいなと思っていたら、上美生の移住仲間が関木材工業でたまたま働いていて、新しく工場を建てるのに人が必要になるからと、仕事を紹介してくれたんです」
平成7(1995)年に完成した屈足工場で働くことが決まります。とはいえ、木材業界も初めてで、工場で働くのも初めて。
「機械を触るのももちろん、初めてのことばかりでしたが、工場自体も国内初の2×4の工場だったので、みんなが右往左往していましたね。あのころは、自分もとにかくJAS規格を頭に入れるので必死でした」
当初、屈足工場はトドマツの2×4材の製造だけでしたが、現在は、トドマツを使ったパレット材や梱包材も製造。
「たまに2×4材を手がけることもありますが、今はパレット材のカットをメインで担当しています。パレット材はお客さんのオーダーごとに内容もさまざま。その内容に合わせて、機械を調整しながらカットしていきます。一方で、2×4材は生材を乾燥させてから仕上げていくので、乾燥させた際にどれくらい縮むかも計算して機械にかけ、決められた長さにカットしていきます」
仕事で気を付けているのは、とにかく安全第一での作業。そして、注文通りの長さにカットする際の正確さと話します。また、納品物を運搬するトラックが到着した際に、すぐ積み込めるよう作業の段取りにも気を使うそうです。
「自分が考えた段取り通りに作業が進んで、時間通りに終わると、『今日もよくやった』と思いますね。その日のうちにやるべきことが予定通り終わると、次の日からの段取りもスムーズにいきますからね」

現在、屈足工場には14人のスタッフが仕事をしています。若いスタッフから福田さんのようなベテランまで幅広い層が在籍。職場の雰囲気を尋ねると、「みんな仲良くやっていますよ。互いに技術を教え合ったりしながら、和気あいあいとしています。若いスタッフと一緒に仕事していると、自分も気持ちが若返ります」と教えてくれました。
30年続けてこられた理由を尋ねると、「居心地がいい職場なんですよね。木材を扱う仕事との相性もいいのかな」とニッコリ。人間関係はもちろん、福利厚生などの手厚さも大きいと話し、「この会社に出合えたのは本当にラッキー」と続けます。
「体が動くうちはまだまだ働きたい」と話す福田さん。本当に働きやすく、良い職場環境なのだなと感じました。




























