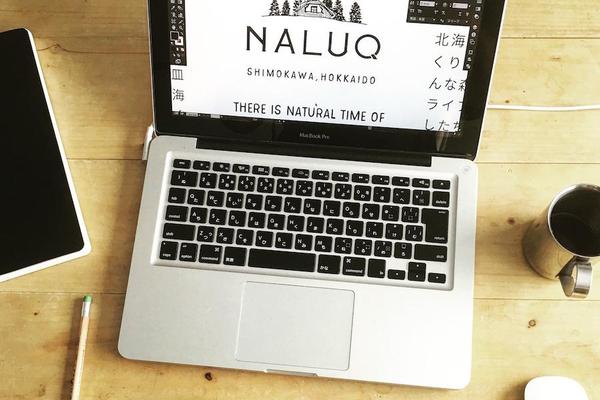道北にある下川町は、町の面積のうち9割が森林。道内でも林業が盛んな町のひとつです。下川町では、木を伐ったあとに植林し、また伐採して植えるという循環型森林経営を続けています。さらに伐って製材するだけでなく、チップにして木質バイオマスボイラーの燃料にしたり、炭、精油に加工したりするなど、余すことなく資源を有効活用しているのも特徴です。今回はその下川町で森の仕事に携わっているステキな田邊大輔さん、真理恵さん夫妻を取材。町外出身の2人がどういう経緯で下川町を訪れ定住に至ったのか、また、下川町での暮らしや仕事のことなども伺いました。
森林の仕事に就きたい。下川町の林業への取り組みに惹かれ、東京から移住
夫の田邊大輔さんは下川町の森林組合を経て、2021年に独立。株式会社田邊林業代表として林業における「川上」の部分、森づくりから木材を生産するまでの仕事に従事しています。妻の真理恵さんは、下川町のトドマツ(北海道モミ)から精油を抽出し、商品化している株式会社フプの森の代表取締役です。事業としては、森林資源を活用し、消費者の手元に商品を届ける「川中」「川下」の部分にあたります。さらに、夫妻は下川町や近郊の木材を使って自宅も建設中。川上から川下までをよく熟知している夫婦ということになります。宮城県出身の大輔さんと、千歳市出身の真理恵さんが出会ったのは下川町。まずは2人が出会うまでを、順番に伺っていくことにしましょう。
 夫の大輔さん。株式会社田邊林業の代表として、下川の森林で林業に携わっています
夫の大輔さん。株式会社田邊林業の代表として、下川の森林で林業に携わっています
大輔さんが生まれ育った宮城県のまちは、家の裏に山がある自然に囲まれた場所だったといいます。
「いつも自然の中で遊んでいましたね。高校卒業後は、旭川にある東海大学でデザインや建築について学びました。大学を出たあと、東京のデザイン建築関係の事務所で働き始めたのですが、当時の日本では国産材の自給率が低く、外材主体のものづくりを強いられていました。したがって国内では間伐が遅れ、質の高い木材の供給ができない状況にありました。
子供の頃から親しんできた身近な森林が荒れている状況を黙って見ていられなかったというのもあり、林業の世界に入ることを決意します。まずは東京都の森林組合で半年間研修を受け、そのあと、働く場所を北から順に探そうと思って、各地の森林組合をネット検索していたら、当時ホームページを持っていたところは少なかったんですが、下川町の森林組合にはホームページがあったんです。そこに森に対する熱いことが書いてあってそれに共感して、すぐに連絡をしました。2004年のことです」
下川町の森林組合は、循環型の森林経営をしているほか、伐採した木をただ販売するだけでなく、木材に価値を付ける加工事業にも取り組んでいました。捨てられることが多かった間伐材の活用や、使われることのなかった枝葉を用いて精油を抽出するなど、資源の有効活用を積極的に行っていました。そうした活動にも魅せられ、大輔さんは下川町へ。
 木の枝葉を蒸留して精油を抽出。蒸気とともに森の爽やかな香りが広がります
木の枝葉を蒸留して精油を抽出。蒸気とともに森の爽やかな香りが広がります
「当時の組合長は、新入りには組合で行っている全ての部門でまず働いて、森の入り口から出口まで携わる中で林業の経営感覚を身につけてもらおうという考えでした。組合に入ってちょうど1年が経とうとしていた頃、精油事業の担当をしていた方が退職することになったんです。自分はもともとデザインをやっていたこともあり、ブランドのデザインや商品開発などの部分でお役に立てるかもということで、精油事業に就くことになりました」と大輔さん。
森の学びを深めるため、一度下川町を離れて大学へ。再び戻り、林業に従事

2年ほど精油事業を担当したあと、「もう少し森について学びたい、何か吸収したいと、自分の中でくすぶりはじめていて、1回下川町を出ることにしたんです」と大輔さん。でも、このときいつか下川町には戻ってこようと考えていたそう。
「下川でできた人との繋がりは大きかったし、大事にしたかったんです。それに、下川の森づくりやそこから製品を生み出そうとしていたところはとても気に入っていましたから」
下川町を一旦出た大輔さんは、伝統工法と言われる建築の勉強をするために宮城の大工のところで技術を学び、その後、信州大学の農学部で林業について学びます。そして、2008年の秋に下川町へ戻り、農業の6次化の手伝いなどをしながら、再び森林組合で仕事がしたいと考えます。
「外で学んできたことを下川の森づくりや産業のために活かしたい、もう一度チャンスをくださいと、組合長に何度も交渉したところ、条件付きで了承してもらえました。クラスター推進部というシンクタンクで半年間働いたのちに再び森づくりの現場に戻ることになったんです」と大輔さんは振り返ります。
大輔さんの本気度はきちんと伝わっており、組合で森づくりに携わる中、緑の雇用制度を使って必要な林業の資格を取得できるリーダー研修も受けさせてもらうなど、町の林業の次世代を担う存在として期待されていたようです。約10年勤務し、2018年に組合を退職。次は原木・丸太を輸送する地元の会社で働きはじめます。
「漠然とですが、40歳くらいで独立したいと考えていました。林業の川上から川下まですべて見ておきたいというのもあり、丸太の流通のことも学びたいと思っていたんです。ちょうど町内でバイオマス発電所が稼働し始める時期と重なり、各地から発電所に原木を運ぶ仕事や土場での原木受け入れ作業を担当させてもらいました」
そして2021年、ちょうど40歳のときに独立し、現在は町有林や私有林の造林、造材などを行っています。

違法伐採などで緑がなくなってしまう...。学問や調査から環境の世界へ
 妻の真理恵さんは千歳市出身。木の精油などを商品化する「フプの森」の代表です
妻の真理恵さんは千歳市出身。木の精油などを商品化する「フプの森」の代表です
次は妻の真理恵さんが下川町へ来るきっかけ、フプの森の代表になるまでを伺っていきましょう。
「私は千歳で生まれ育ち、夫と違って森林とは無縁な生活を送っていましたが、でもテレビで見る自然や森に憧れは持っていました。中学生くらいのとき、違法伐採の木を日本人が使っているという話やそんなことを繰り返しているうちに世界の各地の森がなくなっているという話を聞き、子どもなりにこれでいいのだろうかと考えていました」と真理恵さん。
高校時代に出会った生物の先生が生態学の研究者でもあり、「その先生の授業がおもしろくて森林や植物、環境について興味を持ち始めたんですが、文系だったので環境経済なども学べる経済学部へ進みました」と真理恵さん。北海道大学の経済学部へ進学し、生態学の調査を行う自然保護研究会というサークルに入ります。
「学生時代は知床や大雪山へ行って、対象区域内の立木の樹種や太さを測定する毎木調査を行っていました。そのころからトドマツの香りが好きで、トドマツのヤニをつけて喜んでいましたね」と真理恵さんは笑います。
森林に関わる仕事がしたいと考えていましたが、「伐倒とかバリバリの林業は無理かも...、森の研究者と言っても経済学部だし...」と思った真理恵さんは、「植物」という括りで考えて札幌の生花店に就職します。
「それでもいずれ森に関わる仕事がしたいという思いはありました。生花店の仕事を2003年にやめて、何か情報を得られるかなと思って東京でやっていたエコプロダクツ展(環境配慮型製品や技術、サービスの展示会)に行ってみたんです。そこで森林認証のシンポジウムを開催していた方に、森に関わることで自分にできることはないかと相談してみたら、『北海道なら下川町でしょ』と言われたんです」
北海道に住んでいるものの下川町は知らなかったという真理恵さんは、まず下川町について調べます。すると、北海道で初めてFSC認証を取得していると分かり、森林組合へ森を見せてほしいとメールを送ります。このFSC認証とは、生物多様性を守り、適切に管理された森林で生産した製品にだけマークを付けられる国際的な認証制度。違法伐採などから森を守ることにも繋がっています。
「森を見るために下川町を訪れ、そのとき初めてトドマツの精油事業をしていることを知りました。トドマツの香りが好きだったこともあり、やってみたいと思ったのですが、そのときは精油担当のポストが空いていなくてすぐに移住というわけにはいかず、そのあとは何度か下川町へ足を運んだり、札幌の催事に出店するときに顔を出したり、ファンのような感じで関わらせてもらっていました」
昔から好きなトドマツを使った精油づくり。「フプの森」として会社を設立

札幌でインターネットに関する仕事をしながら、下川町との繋がりも温めてきた真理恵さん。初めて下川町を訪れてから3年ほどたったあるとき、下川町やイベントなどで顔を合わせていた大輔さんから「森林や木について学ぶので下川を離れます」と手紙が届きます。真理恵さんは、「それなら精油事業の後を引き継ぎます」と立候補。2007年の冬に下川町へ移住を果たします。そのころから2人は交際もスタート。真理恵さんが下川町へ移ると同時に大輔さんは下川町を出てしまい、「最初から遠距離でした」と笑います。

精油事業は森林組合の事業でしたが、真理恵さんが大輔さんの後任として入ったときには、森での体験事業を行っていたNPO法人森の生活に事業移管することが決まっていました。真理恵さんは、1年目は森林組合の職員として精油事業に取り組み、翌年にはNPO法人森の生活へ転籍。その際に、ブランド名を「HOKKAIDOもみの木」から「フプの森」に変更します。「フプ」とはアイヌ語で「トドマツ」のこと。
その後、NPO法人から精油事業を移管し、2012年、真理恵さんは精油事業の先輩の女性とともに株式会社フプの森を立ち上げます。

フプの森の製品のパッケージデザインなどは、2008年に下川町へ戻っていた大輔さんに依頼。2014年には社有林を購入し、2015年からはライフスタイルブランド「NALUQ(ナルーク)」を立ち上げます。トドマツの精油や森の植物エキスを配合したバスミルク、ボディミスト、ハンドクリーム、キャンドルなどを展開。石油系界面活性剤や合成香料など不使用で、自然な森の香りが評判です。
「精油だけでなく、もっとアイテムを増やしたいと思っていたときに、地方発の未利用資源を使って社会的意義のある化粧品を作るOEMの会社の方を紹介してもらい、ブランディングから一緒に取り組み、NALUQシリーズを作りました。こちらもデザインは大輔が担当しています」
NALUQシリーズは道内のオーベルジュなどでも置かれているほか、北海道のお土産としても人気があるそう。また、かつては東京へ営業をしていましたが、株式会社になってからは逆に道内からの引き合いが増え、「北海道に暮らす人たちが地域に目を向け始めているのかなと感じています」と真理恵さんは話します。
程よい規模感で、自分たちで自分たちの暮らしを作っている実感が持てる町

さて、下川町の森が結び付けた2人。仕事も暮らしも常に森のそばにあります。森が好きな2人らしいエピソードが結婚式。2010年に結婚した際、挙式は下川の森の中で執り行ったのです。バージンロードは、町内にある五味温泉の裏手の森の中の遊歩道。途中、チェーンソーで大輔さんがトドマツを伐倒し、真理恵さんが枝葉を取り、それをパーティー会場に設置した小型の蒸留器を使って蒸留。残りはフプの森スタッフが工場で蒸留して、後日精油にして参列者にプレゼントしました。
 結婚式のトドマツ伐倒シーン。田邊さんご夫妻ならではのウェディングですね
結婚式のトドマツ伐倒シーン。田邊さんご夫妻ならではのウェディングですね
2015年には娘の萌未ちゃんが生まれます。真理恵さんは「NALUQのブランディングをやっている最中で、出産後すぐに病室で打ち合わせしているような状況でした」と笑います。当時、森林組合にいた大輔さんは「僕、組合で初めて男性の育休を取らせてもらいました」と振り返ります。
下川町に暮らしてみていいなと思うところを伺うと、「緑が近くにあって、サイズ感もちょうどよく、知り合いが多いので安心感があります。あと、まちづくりに関して声をあげたら届くのがいいですね。都会だと人も多すぎるし、声をあげること自体を最初から諦めてしまうけれど、下川くらいのサイズの町だと、こうしたらいいんじゃないかと意見を言えるんですよね。だから、自分たちが暮らしを作っているという実感があります。自分が直接関わっていないことでも、知っている人がやってくれていると、感謝の気持ちも湧きますしね」と真理恵さん。
大輔さんは町の人について、「下川は大らかな人が多いし、みんな自由な部分を持っている」と言います。「僕のような出戻りでもチャンスを与えてくれるし、しぶとく続けていたら認めてくれる」と続け、「町の人の所有している山の整備なども請け負っていますが、山というのは所有している方の財産なので、それを預けるには信頼がないと難しい。そういう意味では、20年かけてここで頑張ってきたことを認めてもらえたのかなと感じています」と語ります。
森林資源に恵まれた町で、次世代がイメージできる暮らし方や働き方を見せる

移住から15年以上経ち、2人ともすっかり町に溶け込んでいます。冒頭でも触れましたが、この度新しく家を建てることに。もうすぐ完成なのだそう。
「町内で伐採した木を中心に、近隣で調達した木材で建てています。ほぼ100%道産材です。この家を下川の木を使ったモデルハウス的にできたらなと考えています。クラフトや精油など、下川の木はいろいろなものに使えますが、一番使うものといえばやっぱり住宅。身近な森林から収穫した木材だとしてもこれだけクオリティの高いものがつくれるというのを自分の家を通じて提案したいと思っています。
設計は、北海道のことや北海道の木のことをよく分かっている札幌の建築士の須貝日出海さんにお願いして、施工は下川に移住してきた後輩の旦那さんにお願いしました。彼は元家具職人で、センスも精度も超一流です。若園工務店という屋号で道北一円で活躍しており、後輩である奥さんは、昨年『月と野菜』という、量り売りと喫茶のお店を町内で開業しました」と大輔さん。
また、今回の家づくりでは実験的なことも行っているそうで、「一般的に流通する材料に一工夫加え意匠性の高いデザインにしたり、構造モジュールをシンプルにすることで製材工場や大工の手間を削減する狙いもありました」と大輔さん。
さらに、外壁貼りや土壁塗りのワークショップを近隣の住民や子供たち、友達などを呼んで行いました。
大輔さんは「子供たちが将来自分たちで家を建てるときや普段のDIYのときに身近の自然素材を使ってほしいなという思いもあって、こういう経験をする機会を設けました」と話します。大輔さんと真理恵さんがここで根を張り、子育てをしているからこそ、町の未来を担う子どもたちのためにできることをしたいという考えになるのでしょう。
「下川町は幼稚園から高校まで森林教育を行っているんです。僕も今年から中学1年生のフィールドワークに関わらせてもらっています。循環型の森林経営を町に暮らす子どもたちにも伝え、林業や森林活用が彼らの将来の仕事の選択肢の一つになればと思っています」と大輔さん。
真理恵さんも「フプの森や精油事業は自分たちだけのものとは思っていません。これからも町の人たちの意見も聞きつつ、事業を残し、次世代へバトンを渡していければと考えています。そして、下川町の森林を活用してこういうこともできるんだなということを若い人にも知ってほしいし、フプの森が活用事例のひとつになれればと思っています」と話します。
さらに大輔さんは、役場の森林関係者や町内で森づくりに興味がある人らを集め、「未来の森づくり」(仮)というグループを作り、定期的に集まって勉強会を開いたり、町有林を見て回ったりしています。
「これからの森づくりを考えていかなければならない時期だと感じています。このまま人工林だけやり続けるのが良いのか、それとも町の林業のもう一つの手札として近自然森づくりのような手法を取り入れた天然林施業も取り組む必要があるのではなど、どのようにアプローチしていくのが良いのか、皆で考え、話し合っています。
長い目で見て、環境と経済のバランスが取れた森づくりをしていきたいですね」
と今後への思いを語ってくれました。
下川町の豊かな森とともに暮らしている田邊夫妻。木が育つのには時間がかかりますが、10年、20年先を見据え、どう森を育てていくかを決めていかなければなりません。慌ただしく日々に忙殺されていると、目の前のことしか見えなくなりがちですが、夫妻の話を伺っていて、大人たちが責任を持って未来について考えることがいかに大事かをあらためて教わった気がします。そして、2人が下川の森と町を本当に大切に思っているのが話を伺っていて伝わってきました。