
チーズの本場、ヨーロッパでも高評価!
個性豊かなメンバーが寝食をともにして働く農事組合法人共働学舎新得農場。動物のお世話や畑作、農産加工品づくりなど、数ある仕事の中でも大きなウエイトを占めているのがチーズづくりです。同農場はチーズに最適なミルクを搾れるブラウンスイス種を中心に、春から秋にかけて通称「牛乳山」の麓で牛たちを放牧。農薬や化学肥料に頼らずに、自然のおいしさが凝縮された生乳から高品質なチーズを生み出しています。丁寧に仕込んだ商品は、チーズの世界大会で金賞を獲得するなど、チーズの本場ヨーロッパ諸国でも高い評価を受けているのです。

牛乳がニガテな酪農家の後継者!?
札幌から新得へとクルマを走らせること約2時間半。スーパーや飲食店が集う小さなマチナカを抜け、しばらく進むと「共働学舎新得農場」の看板が見えてきました。駐車場の目の前には、チーズ料理が楽しめるカフェとショップを兼ねた「ミンタル」が佇んでいます。ナチュラルでおしゃれな雰囲気に目を奪われていたところ、「コッチですよ〜!」という声が聞こえてきました。元気な笑顔で迎えてくれたのは畠山楓さん。高校を卒業したばかりのフレッシュな18歳です。

「両親は隣の清水町の酪農家。二人で100頭くらいの牛の面倒を見ています。私は小さなころから両親の働く姿を間近で目の当たりにしてきて、どんなに仕事が大変な時でも笑顔を絶やさない芯の強さにあこがれていました。中学3年生で進路を考えた時、ウチの酪農に役立つことを学びたいと帯広農業高校へ進学することに決めたんです」
畠山さんが高校時代に描き始めた夢。それは、将来的には牧場の経営や生産を弟に任せ、その牛乳を使ってチーズをつくることです。
「私、酪農家の娘のクセに牛乳が好きじゃなくて...幼いころに両親から飲まされすぎたんでしょうね(笑)。ただ、乳製品の中ではチーズがとりわけ大好き。なので、牛乳が苦手な人がつくるチーズって、インパクトが強いし説得力もあるんじゃないかと思ったんです」

高校卒業後は中標津のチーズづくりに取り組んでいる牧場で働きたいと考えていましたが、残念なことに離農してしまったのだとか。進むべき道を迷っている中、担任の先生から紹介されたのが同農場。あまり好きではなかったという白カビのチーズも、ここの商品なら苦みやクセがなくおいしいと感じていたそうです。畠山さんにとっては渡りに船。すぐに2年間の研修生として働くことにしました。
チーズづくりには同じ作業が一つとしてない。
お話が一段落したところで、畠山さんが案内してくれたのは同農場のチーズ工房。メインの作業場と生乳を殺菌するタンクとの間には段差があり、ちょっと不思議な構造です。一見すると動線が良くないような...。

「実は、この高低差がおいしいチーズをつくるためのポイントです。チーズ工房は牛舎の搾乳室より低い場所にあり、絞りたての生乳がパイプを伝って自然に流れてタンクに運ばれます。生乳を揺らして質を損なうことがないように工房内にも高低差をつけて、自然流下させているんですよ」
なんとも驚きの仕組み。畠山さんはそんな同農場のこだわりを学びながら、1カ月ほどかけて作業の流れを覚えていきました。次の1カ月ではカマンベールチーズづくりを実践。基本技術に加えてスターター(発酵を進めるための乳酸菌や酵母など)やレンネット(酵素)を添加するタイミング、乳の固まり具合の感触を教わりました。

「共働学舎のチーズは有名だから1年間は下積みを覚悟していました。でも、先輩方は『少しずつ覚えていこう』と早くから製造に携わらせてくれてビックリ!とはいえ、生乳の発酵具合によってレンネットを添加するタイミングを変えたり、ミルクの脂肪分が高い時は水分が抜けやすいようにプレスしたり、同じ作業でも日によって微調整が必要。チーズづくりは本当に難しく、奥が深いです」
畠山さんは同農場のチーズ工房では一番の後輩。仕事中も休憩中も、先輩から可愛がってもらっていると微笑みます。「ウチの農場には『カエデちゃん』という牛がいるんですが、私の名前も楓。先輩が『カエデ〜!』なんて呼んでいると、たまにどっちのことか分からなくなったり(笑)」
 楓さんと、牛の「カエデちゃん」のツーショット。
楓さんと、牛の「カエデちゃん」のツーショット。
研修生は敷地内の寮で暮らし、食事は朝昼晩とみんなでワイワイ楽しむスタイル。親元を離れても、大勢で家族のように過ごすなら寂しくはない?
「う〜ん...高校のころも寮住まいだったんですが、クラスメイトとの二人部屋。今は仕事が終わって一人の時間も多いから、ちょっとシンミリすることも...。そんな時は友だちに電話したり、休日に帯広や広尾にドライブに出かけたりして気分転換しています。あと、最近はインスタでも友だちと交流しています。きれいな景色をアップロードして『イイネ!』がつくとやっぱりうれしい(笑)」
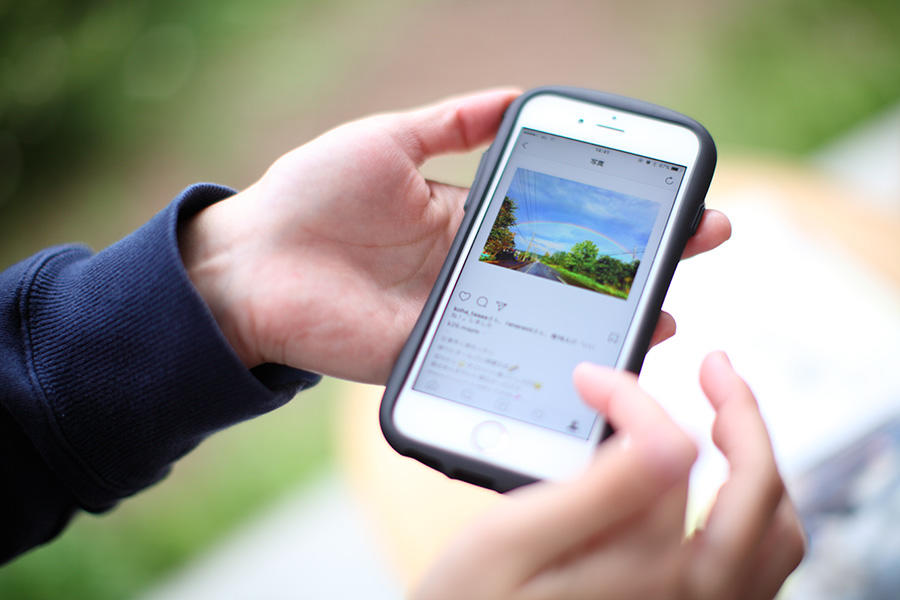 畠山さんがインスタにアップロードした虹の写真。
畠山さんがインスタにアップロードした虹の写真。
チーズづくりは、両親への「ありがとう」。
畠山さんは、同農場の研修生として働き始めてまだ4カ月。技術の習得で目一杯だとは思いますが、ここの研修を終えた後の未来予想図を尋ねてみました。
「いきなり実家に戻ってチーズづくりを始めるにはまだまだ実力も知識も足りません。まずは日本各地のチーズ工房を見学したり、ゆくゆくは海外にも勉強に行ってみたいと思っています。両親は私が進みたい道に対して反対したことはなかったので、きっと胸を張って送り出してくれるはずです」

畠山さんがご両親に絶対の信頼を置いているのには理由があります。彼女は小学生のころに陸上競技を始め、高校時代は槍投げの選手として全道大会に出場するほどの実力でした。お母さんは試合会場が旭川でも釧路でも、必ず応援に駆け付けてくれたそうです。
「父は一人で作業するのが負担にも関わらず私の記録を気にしていましたし、母は『あなたのおかげでいろんな土地に旅行させてもらってるの』といってくれました。恩返しの言葉を口で伝えるのは照れくさいけれど、両親が頑張って搾った牛乳をチーズという形にして、ありがとうの気持ちを込めたいんです」

こんなふうに同農場にはチーズづくりを学びたいという若者が絶えず訪れ、そして新たな夢に向かって巣立っていく人を見守っています。
「当農場で研修して自分のチーズ工房を開くメンバーもいます。代表の宮嶋は包み隠さずなんでも教えるタイプですし、いつも皆さんのことを気にかけているんです。例えば全国各地に居る研修を終えた人たちのところに顔を出したり、電話でチーズづくりのアドバイスしたり、まるで『実家の親』みたいなおせっかいを焼いています(笑)」と教えてくれたのは同農場で長く働く加藤英雄さん。取材の締めくくりにこう言葉を続けました。

「例え同じ製法でもその土地の空気や水、そして微生物によってチーズの味わいはガラリと変わります。うちで研修した後にそれぞれの場所で、土地に合ったおいしさをつくってくれればうれしいですね。とはいえ、私たちも次の世代のことを考えなければならない時期に入ってきました。ここでさまざまな人と暮らしながらおいしいチーズをつくるという幸せな生き方に共感し、『実家に残る』メンバーが増えるように取り組んでいるところです」
数年前からは新得の役場や農協と手を取り合い、新得を「チーズのまち」に押し上げる構想も動き出しています。具体的には同農場の2番目、3番目となるファームをまちに展開し、若い酪農家をバックアップしながらチーズづくりの技術や販路を提供していく予定。多くの人々が新得という地域で一緒に生きていけるよう、チーズを柱に新たな取り組みに挑戦しているのです。





















