
くらしごとの中に「海スタイル」という括りがあります。北海道の漁業・水産業に関わっている人々の想いや魅力を「伝える」ことで、少しでも漁業・水産業の力になれればと記事を発信しています。私たちと同じように「伝える」ことで、愛する北海道の漁業を盛り上げたいと活動しているのが、ラジオパーソナリティーやテレビのお仕事で活躍しているとついようこさんです。
元気いっぱいの「浜ばか」ラジオパーソナリティー・とついようこさん
現在、STV(※)の地元応援型通販番組「情熱市場」に出演中のとついようこさん。コミュニティーFMラジオのFMドラマシティの昼の情報番組「ランチタイムバラエティ・ディッシュ」の金曜担当パーソナリティーとしても活躍しています。テレビで見るより小柄な印象ですが、とってもパワフル。「めちゃくちゃ喋りますよ、私」と、部屋に入った瞬間から周りをグッと引き付ける明るさで、ほぼ初対面にも関わらずこちらも笑顔になります。
※ STV札幌テレビ放送の略
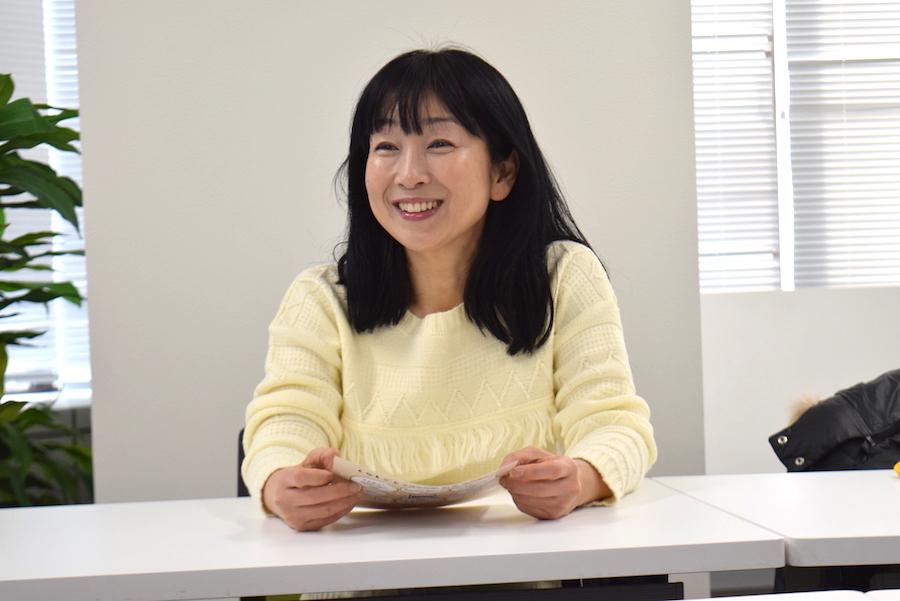
くらしごと編集部がとついさんを知ったのは、漁業関係者の集まり。くらしごとでも漁村訪問などの記事を掲載している、北海道大学水産学部の学生による団体「レディ魚ー(レディゴー)」のメンバーとのご縁がきっかけでした。
自身のことを「北海道の浜を愛する浜ばか」と称するとついさん。STVの長寿番組「どさんこワイド」内の「北海道の浜から産地直送」(通称/浜直)の専属リポーターとして全道各地の浜を回ったのを機に、「浜ばか」になったと笑います。専属リポーター時代、漁船に乗った回数は200回を超え、道内の浜は4周もしているそう! 浜直のコーナーが終わったあとも、全道の浜へ足を運び、漁師さんや浜の母さんたちと親交を深め、そこで見て、聞いて、感じたことをラジオやSNSを通じて紹介しています。
 おさかなととついさん。とっても楽しそう
おさかなととついさん。とっても楽しそう
さて、和歌山県出身のとついさんが、どういった経緯で北海道へやってきて、なぜ漁業に対してそこまで熱いものを持つようになったのか、これまでの歩みとこれからのことを伺っていきたいと思います。
熊野の山で生まれ育ち、高校時代の夢はインドでジャーナリストになること⁉
「熊野地方の山奥で生まれ育ちました。イノシシもサルもいるようなところでしたね。祖父がみかん栽培と稲作の農家を営んでいて、幼いころは山の中を駆け回っているようなお転婆な子でした」

自然豊かな環境で育ったとついさんですが、就学前に今でも忘れられない自然の厳しさを突き付けられる出来事を経験します。
「大きな台風が直撃して、祖父が大事に育てていた田んぼの稲がほぼ全滅してしまったんです。祖父は部屋に引きこもってしまい、そのひどい落ち込みようは子どもには衝撃でした。自然の持つ残酷さを初めて目の当たりにしました」
自然は私たちに恩恵を与えてくれる一方で、ときに脅威となることもあると幼心に強烈に感じたそう。
その後、父親の仕事の関係で埼玉へ移り住み、そのまま地元の高校に進学。当時よく読んでいた椎名誠や野田知佑らの旅行記などの影響もあり、「なぜかインドで活躍するジャーナリストになりたいと思っていました」と笑います。
大学で出合った演劇の世界。現実に打ちのめされ、抜け殻状態で北海道へ
「ジャーナリストといえば早稲田の政治経済学部だろうって思って、浪人したんですけど、同じ早稲田でも結局文学部に入りました(笑)」
そこで、その後のとついさんの人生を大きく左右する「演劇」と出合います。演出家の鴻上尚史や俳優の堺雅人ら、多くの著名な演劇人を輩出している早稲田大学演劇研究会に入り、女優として演劇に打ち込みます。
「商業演劇に夢中になって、在学中に演出家の蜷川幸雄さんが主宰していたニナガワカンパニーに入りたいと門を叩いたら、学生はダメだと言われ、大学を中退して蜷川さんのところへ行きました」
一般的な養成所とは異なり、メンバー同士で戯曲を選び、自分たちで稽古。その舞台を見た蜷川氏が自身の舞台に出してもいいと思う若手がいれば採用という常にオーディション状態のシステムでした。当然無給で、とついさんもアルバイトをしながら稽古に励んでいました。
「何度か群集役の一人や代役で蜷川さんの舞台には立たせてもらいましたが、あるとき、ふと自分は商業演劇の女優に向いていないかもと思ったんです。ちょうど28歳になったころでした」
すべての情熱を演劇に注いでいたとついさんは、そのとき魂が抜けたようになっていたと振り返ります。そして、夜逃げ同然で北へ向かいます。
 このような将来が待ってるなんて想像もしてなかったことでしょう
このような将来が待ってるなんて想像もしてなかったことでしょう
「なぜか、北へ行きたくなったんですよね。求人誌をめくって、住み込みで働ける場所を探し、十勝の中音更にある牧場で働くことにしました」
慣れない環境で朝から乳牛の世話をする毎日。最初は抜け殻状態で、ただただ言われた通りに牛舎の掃除、エサやり、搾乳をしていたと言います。
「掃除や搾乳のとき、どうやっても言うことをきかないメス牛が1頭いたんです。その牛、パンダみたいな顔をしていたから、パンダって勝手に呼んでいたんですけど、パンダと格闘しているうちに、空っぽになっていた自分の心に感情というものが戻ってきて、外にわぁーって感情を出すことができたんです」
3ヵ月働いたあと、「このまま跡を継いでもらえないか」と相談されますが、もう一度自分らしい挑戦をしたいとその申し出を断り、とついさんは札幌へ。飲食店でアルバイトをしながら自分の進む道を模索していると、知り合いになった人から「テレビのショッピングコーナーに出てくれる子を探すオーディションがあるよ」と紹介されます。
ひょんなことからテレビのリポーターになり、全道の浜を巡ることに
オーディションの内容も詳しく聞かないまま、とりあえず受けに行ったというとついさん。北海道に来て数か月、道内の地名の読み方なども分からず、渡された台本に書いてあった「月寒(※)グリーンドーム」を「げっかんグリーンドーム」と読み、笑われたそう。
※ 月寒(つきさむ)は、札幌市豊平区にある地名。
 毎週金曜日は、FMドラマシティの昼の情報番組「ランチタイムバラエティ・ディッシュ」にて浜の情報発信中
毎週金曜日は、FMドラマシティの昼の情報番組「ランチタイムバラエティ・ディッシュ」にて浜の情報発信中
「もう落ちたなと思っていたら、そのオーディションの審査に参加していたどさんこワイドのプロデューサーが、牧場で働いていたという経歴を見て、体力もありそうだし、浜をまわる浜直のリポーターをやってみないかと声をかけてくれたんです」
ここから、とついさんと浜の関係がスタートします。山で育ち、牧場で牛の世話をした経験があるとはいえ、海や漁業関連に携わるのは初めて。「浜直で最初に取材へ行ったのは道東の厚岸町(あっけしちょう)のサンマ漁だったんですが、ヒール3㎝くらいのパンプスで現地に行ったら、船に乗るのにそんな恰好はダメだ、長靴に履き替えろって言われて(笑)。そのころは、海のことも船のことも何も知らなくて、リポーターだしと思って最初はちょっとツンツンしていたんです」と笑います。そして、その初リポートでなんと18時間も船に乗っていたそう!

えりも沖、船酔い中。これも修行!

伝えたい! 現場で感じた大事なことはすぐにメモ
「今から20年くらい前になりますが、当時はどこの浜も活気があって賑やかでした。漁協の数も今よりももっとありましたしね。たくさんの漁師さんや浜の母さんに取材して、それぞれの海産物のストーリーを浜直の番組で伝えていく中で、私自身、いっぱい元気をもらったし、命のありがたさを強く実感するようになりました」
こうした経験をもとに、現在は漁師さんと一緒に子どもたちの食育の出前授業を行ったりもしているそう。浜直のリポーターを務めた4年半の経験は、今のとついさんの活動の原点となりました。
 三石(※)での昆布の出前授業の様子
三石(※)での昆布の出前授業の様子
※新ひだか町にある三石(みついし)地区のこと。
人気ラジオ番組のアシスタントに。語りの師匠・日高晤郎氏との出会い
その後、食や温泉情報のリポーターとしても活躍していたとついさん。38歳を迎えるころ、STVラジオの看板番組のひとつだった「ウイークエンドバラエティ 日高晤郎ショー」の16代目アシスタントとして番組に出演します。
「ある日、たまたまロケ車に乗っているとき、日高晤郎さんがしゃべっているのを聞いたんです。そのとき、蜷川幸雄さんが舞台を演出しているときのような一流の匂いがしたんです。それで、ぜひこの番組のアシスタントをやってみたいと思って、プロデューサーに相談しました」
アシスタントを4年務め、その後、番組内の中継の30分枠を4年担当。合計8年間、日高氏のそばでたくさんのことを学びます。
「喋りに関してはとても厳しい人でした。ミリ単位で叱られていました。朝稽古しようと言われ、朝早くからマンツーマンで喋りの稽古をしたり、私以外のリポーターや一般の方も学べる月1回の日高塾に参加したり...。大変でしたけど、今はとても感謝しています」
また、日高氏がずっと取り組んでいた「独り語り」の話芸も間近で見てきたとついさん。公演の手伝いのほか、実は、番組内で日高氏が人の生き様を独り語りするコーナーの取材原稿を、毎週担当していたのだそう。
「晤郎さんは台本なしで語りをするんですけど、私が取材してきた素材を見て、そこから語りを始めるんです。いつも、取材は材を取ってくるものだ、人の匂いをかぎ取ってこいって言われていました」
この経験がのちにとついさんがライフワークにしたいと考える「浜語り」に繋がっていきます。
コロナを機に、自分を救ってくれた浜と浜の人に恩返しをしていこうと決意
とついさんが、自らのことを「浜ばか」と称するようになったのは、コロナがきっかけでした。

「コロナ禍に突入して、マイクを持つ仕事が激減。ちょうど50歳という節目を迎えたこともあり、自分の生き方について考えるようになりました。自分が何をやりたいのか、何をしていきたいのか。考えた末に、やはり私は喋るのが好きで、喋りを通してこれまでお世話になった人たちに恩返しをしたいと思いました。抜け殻状態で北海道へ来て、自分には価値がないと思っていた私のことを大事にし、自信を取り戻す力を与えてくれたのは取材を通して知り合った浜の皆さんでした。だから、今度は私が浜のことを喋りで伝え、少しでも恩返しがしたいと思ったんです」

海水温の上昇や、漁獲の落ち込み、後継者不足など、さまざまな課題を抱える水産業界。みんなで課題解決に取り組みながら、浜の賑わいを取り戻したいと、とついさんは自身がパーソナリティーを務める番組で浜のことを紹介し、Facebookでも北海道の浜の情報を積極的に発信しています。その輪は広がりはじめ、応援してくれる人たちが増え、とついさんを介して点と点だったものも繋がり始めているそう。
後継者問題や漁業の就労に関しては、「それぞれの世代が危機感は持っているんです。ただ、若い層と年配の人たちとの考え方の違いや世代間ギャップが大きくて連携が難しくなっています。だからこそ、自分のような中年層が間に入って架け橋となる必要性を感じています」と話します。水産系の大学生らと浜を結びつけるような活動も今後展開していきたいと構想も語ってくれました。
 漁の合間に漁師さんたちと一緒にご飯を
漁の合間に漁師さんたちと一緒にご飯を
漁業関連の講演会に呼ばれることも増えたというとついさん。先日、漁業組合の女性部、いわゆる浜の母さんたちの集まりで90分間の講演を行った際、最後の15分間で「浜語り」を披露しました。浜の母さんの衣装を着用し、自身が取材した浜の母さんの話を日高氏から学んだ「語り」で紹介。すると、涙を流しながら、耳を傾けてくれる母さんたちもたくさんいたそうです。
「これからも自分が浜で取材し、肌で感じてきたものを奥行きのある語りで伝えていけたらと考えています。この浜語りや普段のラジオ、SNSの発信を通じて、浜の温度を上げていきたいです。私、理屈を超えたところで、浜の人のことも、船に乗るのも単純に好きなんですよね。少しずつでもいいから、『浜ばか』普及運動を続けていきます。北海道浜の魅力を知って、浜が大好き!海産物大好き!という『浜ばか』がたくさん生まれたらいいな!」
「求む、『浜ばか』!!」

表情豊かにハキハキと話す様子はさすが喋りのプロ。最後まで笑いを交えながら、テンポ良く話してくれました。いつかぜひ、とついさんの「浜語り」も聴いてみたいと思いました。



















