
旭川の市街地から東神楽町方面へ車で約20分。東旭川と呼ばれるエリアにあるのが、今回取材でおじゃました「農業生産法人 谷口農場」です。明治時代に富山県から入植したのがはじまりで、当初から稲作を行っていたそうです。
また、1980年代後半からトマトの有機栽培をはじめ、1990年代に入るとそれを用いたトマトジュースの製造もスタート。今でこそオーガニックや有機の野菜栽培を行っている農家も増え、加工品作りや六次化に取り組む農家も増えましたが、谷口農場はその先端を走っていたと言えます。
そんな谷口農場について、専務取締役の小関拓哉さんに話を伺ったほか、農産物生産に携わるスタッフ、食品加工製造に携わるスタッフにそれぞれ話を伺いました。
有機や特別栽培の農産物の生産をベースに、加工・販売も行うビジネスモデル

今回の取材で伺った、谷口農場の直売店「まっかなトマト」

店内には、有機トマトジュースや甘酒、お米など様々な商品が並びます
取材に伺ったのは2月前半。今年は例年に比べると旭川は雪が少ないようで、路面が顔を出しているところもあります。専務取締役の小関さんとの待ち合わせは、カフェを併設した谷口農場の直売店「まっかなトマト」。中に入ると、農場で栽培されたお米や自社で加工した有機トマトのジュースやさまざまな甘酒などが並んでいます。夏には新鮮な野菜も並ぶそう。カフェでは、自社の特別栽培米の米粉を使ったチュロスなどを味わえます。
まずは小関さんに話を伺うことに。その前に、「よかったらどうぞ」と勧めていただいた主力商品である有機トマトジュース「ゆうきくん」をひと口...。食塩を用いておらず、トマトそのもののおいしさを感じられます。冬なのに、フレッシュなトマトを味わっているような気分です。発売から30年以上経つそうですが、全国にリピーターや根強いファンが多くいるのも納得です。
そんなおいしいトマトジュースを原材料から作っている谷口農場。小関さんに農場について伺うと、「もともとは稲作農家として作物を作るだけでしたが、現在は有機農業と加工品製造の両方にウエイトを置いています」と話します。
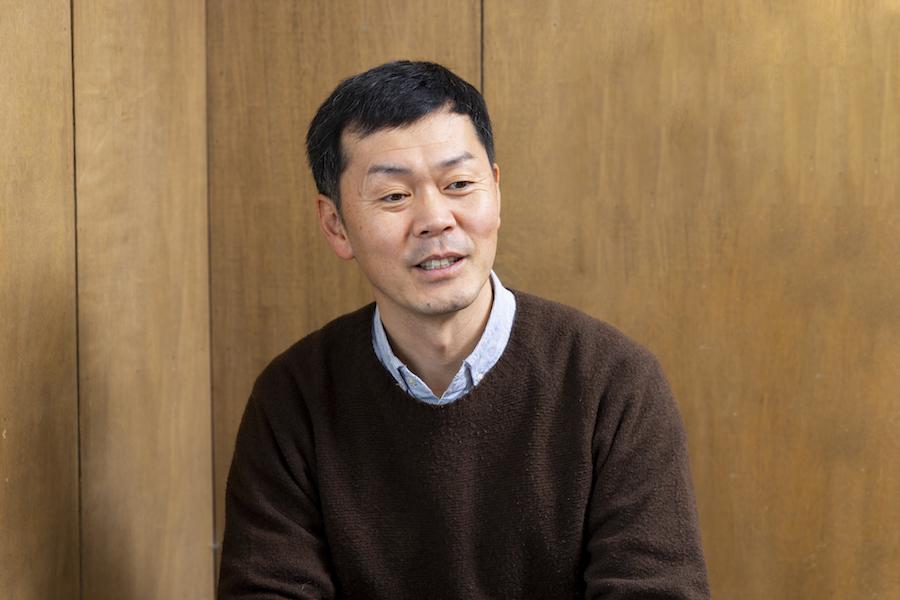 こちらが、谷口農場専務取締役の小関拓哉さん
こちらが、谷口農場専務取締役の小関拓哉さん
「中には、原材料の加工をするのは農家じゃないとおっしゃる方もいますが、うちはその原材料を自社で作っているので農家だと思っています。農産物をよりいい形で表現し、消費者の方たちにお届けするための加工です」と続けます。
トマトジュースのほか、大雪山の伏流水がしみ込んだ水田で栽培される特別栽培米も自慢の商品。ゆめぴりかを中心に、ななつぼし、あやひめ、おぼろづきなどを作っており、オリジナルのブレンド米もあります。取材中も直売店にはお米を買い求めて訪れる旭川や近郊の人が多数。地元で支持されているのがよく分かります。
「トマトもお米も土づくりにはこだわっています」と小関さん。谷口農場では、もみがら、米ぬか、牛ふん、かき貝の粉末、海草、にがりなどが入った自家製のぼかし堆肥を使います。微生物の力で自然に発酵するこの堆肥が、健康な土を作り、おいしい作物を育みます。

早い段階から有機栽培に着手している印象ですが、「有機栽培に関しては、トマトジュースを作るために有機栽培のトマトを作り始めたのが最初です。生食ではなくジュースにするためなので、いわゆる規格外品でもまったく問題ありません。また、昨年からはお米も有機栽培米をはじめました」と話します。
昨年(2024年)11月には、道内の優れた生産者を消費者視点から表彰する「コープさっぽろ農業賞」の「ビジネスモデル賞最優秀賞」に選ばれた谷口農場。有機栽培や特別栽培の農産物の生産を軸に、加工・販売までを自社で一貫して行い、持続可能なビジネスの形を構築してきたことが評価されたそうです。
「コープの農業賞をいただけるとは思っていなかったのでうれしかったです。北海道は農産物の1次加工が弱いんですよね。だから原材料がこんなに作られているのに、大半が道外に農産物が出ていってしまう。でも、うちは加工を自社ですべて行い、販売も手掛けていて、それが強み。そこを評価されたのは大きいと感じています。あと、有機農業をやるなら大きな規模でやらないと採算が取れないんです。うちは、ジュースの原材料のためにトマトを有機栽培しているので成り立っています。作ったものが余ったから加工するのとは逆なのです」

生産、加工、販売と、スタッフの通年雇用を可能にしている多角経営
ビジネスモデルという点で考えると、農業法人としてスタッフの通年雇用ができているというのも谷口農場の特徴。現在45名の従業員が勤務し、仕事に取り組んでいます。一般的な農家の場合、冬は農閑期ですが、加工品の製造やカフェ併設の直売店運営など多角的な経営を行っている谷口農場は冬もいろいろな仕事があります。
「北海道の農家は、冬は仕事がないから別の仕事に就いている場合が多いと思いますが、うちは季節雇用ではなく、通年雇用をしています。冬も加工や販売の仕事があるので、夏に畑で仕事をしている農産物生産の一部のスタッフには、冬になると旭山動物園の売店へ行ってもらったり、スキー場のキッチンカーを担当してもらったりしています。とはいえ、もうトマトのハウスの準備もはじめているので、農産物生産の担当も結構やることはいろいろあるんですよ」
一応、農産物生産、製造、管理、営業とセクションが分けられており、小関さんは現在営業に所属。営業や店舗運営のほか、加工品の商品開発も手掛けていますが、雪が溶けると田畑に出ているそう。

「冬の間に営業や商品開発の仕事をして、3月ころからは畑にも出ます。自分としては、農産物の規格外品を生かした加工品作りを考えるのと、有機栽培のおいしいお米作りが得意。一人で全部できる人なんていないですから、それぞれの得意なところを生かしながら仕事をしてければと考えています」
小関さんは兵庫出身。農業に興味があり、江別の酪農学園大学へ進学します。牛よりも作物に関心があり、卒業時に通年で働ける農家を探していたときに旭川の谷口農場に出合います。
「22年くらい前の話です。当時は夏のみの採用というところばかりで、正社員で通年雇用というところがほとんどなかったんですよね」と振り返ります。入社してからは主にお米栽培を担当。そのうち加工品の企画や営業の仕事にも関わるようになったそう。

「うちは工場があって、1次加工のノウハウがあるのも強み。トマトジュースのほかにも、自社のトウモロコシを使ったコーンスープや特別栽培米の甘酒なども製造しています。また、缶飲料が作れるのでOEM製造も受けています。地元のJAや道内の農家さん、酒造メーカーと一緒に商品を開発しています」
JAあさひかわのさつまいもを使った「さつまいもラテ」や、地元の高砂酒造の大吟醸酒粕の甘酒、東旭川町の守屋農園のにんじんを使ったジュースなどいろいろ。また、飲料だけでなく、自家製みそやゼリー、あんこ、ラーメンなど、加工品のラインナップは多彩です。
「今後は、有機栽培のお米をもっと増やしていきたいと考えています。あとはせっかく工場もあるわけですし、1次加工のノウハウと小ロット対応が可能な点を生かして加工にも注力したいですね」

チームワークはばっちり。トマトの有機栽培を通じて農業の面白さも実感
さて、次は実際に農産物生産、製造の現場で仕事をしているスタッフに話を伺うことにします。まずは入社から20年近くの安部幸一さんです。旭川出身の安部さんは、27歳のときに前職を辞め、次の仕事を見つけるまでのアルバイトで谷口農場へ。製造部で加工品作りを行っていました。
「前職はまったくの異業種で、正直最初から農業に興味があったわけではなかったんです」と笑います。しばらくすると、正社員になって仕事を続けないかと声をかけられます。
 こちらが、農産物生産・製造の現場をとりまとめる安部幸一さん
こちらが、農産物生産・製造の現場をとりまとめる安部幸一さん
「正社員で入社して、それから7年近く製造部で仕事をしていました。そのあと、農産物生産のほうへ異動があり、トマトの栽培を担当。もう10年以上になりますね」
現在は畑作のとりまとめ役を任されている安部さん。もう1人の男性社員、インドネシアからの技能実習生4人、あとはパートスタッフらと一緒に仕事に取り組んでいます。
「チームワークはいいと思います。僕自身、みんなと一緒に働くのが好きなんですよね」と話します。

「今は農業がすごく面白いなと思います。育てた作物を収穫するときの喜びは大きいですね。毎年、最初に食べるトマトがとても美味しいなぁって思うんです(笑)。うちのはやっぱり味が濃いんですよね。有機栽培とかも最初のころは分からなかったんですけど、実際に自分が育てるようになって、食べてみて、味が全然違うし、環境のことも考えたら大事なことだなって今は感じています」
丁寧に作られたトマトは直売店で地元のお客様に、関東のスーパーなどで卸しており、完熟したトマトは自社工場で美味しいトマトジュースになります。
「生食用は表面が割れないように温度管理が必要。あまり暑くなると、割れてしまうんですよね。ハウスの風通しを良くするなど、毎年のようにいろいろなやり方を試しています。自分たちで考えて工夫するのもこの仕事の面白いところですね。すごく奥が深いんですよ」

2月の半ばからトマトの苗を植える準備をはじめ、3月下旬にはある程度成長した苗をハウスへ移すそう。5月ころまで作付けをずらしながら行い、その間に大きくなったものから順に収穫をしていきます。霜がおりるころ、だいたい10月いっぱいまで収穫が続き、11月にはハウスの片づけを行い、次のシーズンに向けての準備をはじめます。冬の間は、敷地内の除雪や機械のメンテナンスなどを行うそう。
「一年通してずっと同じことをするわけではないのも気に入っています。夏場は、天候などによって状況判断しなければならないことも多いですから常に勉強ですし、チャレンジですね。でも、外で仕事をするのは気持ちいいし、もともと体を動かすのが好きなので、畑の仕事は自分には合っていたのかもしれません」
取材に訪れた日は、ハウスの中で、トマトの赤ちゃん苗がやってくるのを受け入れる準備をしていました。チームワークはいいと思うと話していた安部さん。ほかのスタッフも一緒に撮影する際も和気あいあいとした雰囲気で、仲の良さが十分伝わってきました。

さまざまな加工品を工場で製造。新しいことを吸収し、成長している日々
最後に話を伺うのは、昨年(2024年)春に新卒で入った角井亮太さんです。旭川出身で、札幌の大学を卒業後、地元の谷口農場に入社しました。現在は、製造部に所属し、加工品作りに取り組んでいます。
「大学のとき、日本の食糧事情などを調べていて、その際に有機栽培や減農薬栽培の農業に興味を持ちました。地元での就職を考えていたので、旭川エリアで有機栽培をやっているところを探して、谷口農場を知りました。加工品の商品企画やマーケティングにも興味があったので、ここならいろいろなことにチャレンジさせてもらえそうだなと思ったのが入社のきっかけです」
 こちらが、製造部に所属する角井亮太さん
こちらが、製造部に所属する角井亮太さん
入社して製造部に配属となり、最初は分からないことだらけだったという角井さん。
「学生時代にスーパーの総菜コーナーでアルバイトしたことがあって、その感覚で工場に入ったら、まったく規模感が違っていて(笑)。1日にトマトジュースを5000缶とか、1万缶とか、本当にびっくりしました」と笑います。
また、工場ではフォークリフトの運転なども必要で、入社してから資格を取得。「入ったばかりのときはできないことがいっぱいでしたけど、できることも増えて少しずつですけど成長はしているかなと思います」と続けます。

周りの先輩たちはみんな気さくな人ばかりで、すぐに馴染めたそう。
「雰囲気が良くて、皆さんとても親切。分からないこともすぐに教えてくれるし、休憩中も笑い声が絶えません。自分は人と環境には恵まれているなと思います」と角井さん。
製造部で作っているものは、飲料製品を缶や瓶に詰めるほか、お米の精米(取材日はお米の精米の日でした)、あんこ作りなど。ほかにOEMの商品もあるので、手掛けるものは本当に多彩です。

これまで作ったいろいろなものの中で、何の商品が気に入っているかを尋ねると、「あんこですね。自分が今まで食べたあんこのなかで一番おいしいと思います」とニッコリ。
また、「毎日のように有機のトマトジュースを飲んでいるからか、そういえば、入社してから風邪をひいていないですね」と話します。
角井さんは、「製造部は毎日違うものを作るので、日々、いろいろな知識や経験を積み重ねていけるのは面白いなと感じています。農産物生産の手伝いをさせてもらうなど、今後もいろいろな部署の仕事を経験してみたいとは思いますが、入社して1年足らずなので、今は製造部の仕事をもっと深めていきたいですね」と、最後に仕事の面白さとこれからの抱負を語ってくれました。

- 株式会社谷口農場
- 住所
北海道旭川市東旭川町共栄255番地
- 電話
0166-34-6699
- URL
















