
北海道十勝地方の帯広市内にある「有限会社小宮工業」。土木工事や大きな建築物の建設工事で使われる「あと施工アンカー」と呼ばれる施工を中心に事業を展開しています。内勤スタッフ含め、従業員数8名と人数的には少ない印象ですが、手掛けているのは大きな仕事ばかり。それもそのはず、創業者でもある小宮伸行社長は北海道における「あと施工アンカー」の中心的人物。関連協会の役員など要職を務め、道内の「あと施工アンカー」事業をけん引してきました。今回は帯広の本社におじゃまし、仕事内容や会社のこと、社長の想いなどを伺うとともに、従業員の方たちにもお話を聞きました。
「あと施工アンカー」とは? 今後ますます必要とされる仕事
建物の扉を開けると、最初に取材陣を出迎えてくれたのは看板犬のリアンちゃん。人懐っこいリアンちゃんは、興味津々で取材陣のそばに寄ってきて尻尾をフリフリ。その後ろから社長の小宮伸行さんが「どうぞ、どうぞ」と笑顔で中に手招きしてくれます。取材陣が来るということで、この日は社員の皆さんも事務所で仕事をしてくださっていて、楽しげに会話をしている様子からも早速アットホームな雰囲気が伝わってきます。
 取材陣を熱烈歓迎するリアンちゃん
取材陣を熱烈歓迎するリアンちゃん
まずは小宮社長に会社の事業について伺うところからインタビューをスタート。「いろいろやっているのだけど、メインはあと施工アンカーの仕事ですね」。土木・建設業界にいる方なら知っているかもしれませんが、一般的には聞きなれない「あと施工アンカー」という言葉。英語のアンカーは船の錨ですが、建設業界でいうアンカーとは建築資材を固定させるための部品のことを指します。この「あと施工」とはどういう意味なのでしょうか。
「よく聞かれるんですけど、一番わかりやすいのは自動販売機かな。自動販売機が倒れないように足元を固定する際、下地のコンクリートが固まったあとに穴を開けてアンカーで固定するのですが、これがあと施工アンカーです。自販機だけでなく、外付けの看板をはじめ、大きな建物、橋などあらゆる部分で主に安全や耐震補強のためにあと施工アンカーを行っています」
 有限会社小宮工業、代表取締役の小宮伸行さん
有限会社小宮工業、代表取締役の小宮伸行さん
簡単に言ってしまえば、コンクリートで固められたところに穴をあけてアンカーを固定させるわけですが、もちろんそんな簡単なものではなく、構造計算やアンカーの素材、工法など、あらゆることを考慮して、それぞれの現場で作業が行われます。技術や素材も進化しており、奥が深いと小宮社長は話します。
元請会社の設計担当者やメーカーも頼りにするコンサル的な存在
一般社団法人日本建設あと施工アンカー協会の会員でもあり、北海道支部の役職にも就いている小宮社長は、後進育成・資格取得のための一般講習の講師も担当しています。ほかにも大学の研究者や建築資材メーカー、ゼネコンらと共に土木学会のコンクリート委員会のメンバーとしても活動。
「アンカー施工に関しては専門的に長い間携わってきたから、経験と実績はもちろん、技術力や知識もほかの施工会社には負けないものを持っていますよ」
図面を見ただけで強度などが分かる小宮社長を頼って、元請の建設会社の設計担当者らが相談に来ることもあるそう。あと施工アンカーに関して、コンサル的なアドバイスができる施工会社は「道内では数少ないね」と話します。つまり、小宮社長はあと施工アンカーのプロ中のプロというわけです。

「今、全国各地でインフラ関連の設備の補修や改修工事が行われていますが、常に安全性を追い求めるのは当然のこと。改修や補修がなくなることはありません。そういう意味では自分たちの手掛けているあと施工アンカーの仕事はますます重要なものになっていくと考えています」
小宮工業は長年あと施工アンカーの事業を続けている中で、それに付随するさまざまな事業も併せて行っています。ダイヤモンドウォールソーやワイヤーソーでコンクリートの壁をカットしたり、コンクリートの破砕工事やコンクリート壁の空洞やひび割れに注入材を充填するコンクリート空隙注入工事なども行ったりしています。また、耐震関連でアンカーを使う仕事はいろいろあるそうで、下水道管とコンクリート構造物の繋ぎ目に用いられる可とう継手の取り付け工事なども行っています。
これまで携わってきた工事の写真などを見せながら、その内容を説明してくれる小宮社長。十勝管内の橋梁工事では、支承(ししょう)と呼ばれる橋桁を支える構造部材を取り換えるため、ジャッキを使って橋桁ごと2㎜上にあげたという話や、皆が知っている道内の有名ホテルの耐震改修工事を一手に引き受けた話、ダムの壁にワイヤーソーで穴をあけて魚道を新設した話など、さまざまな現場での仕事があるというのがよく分かります。
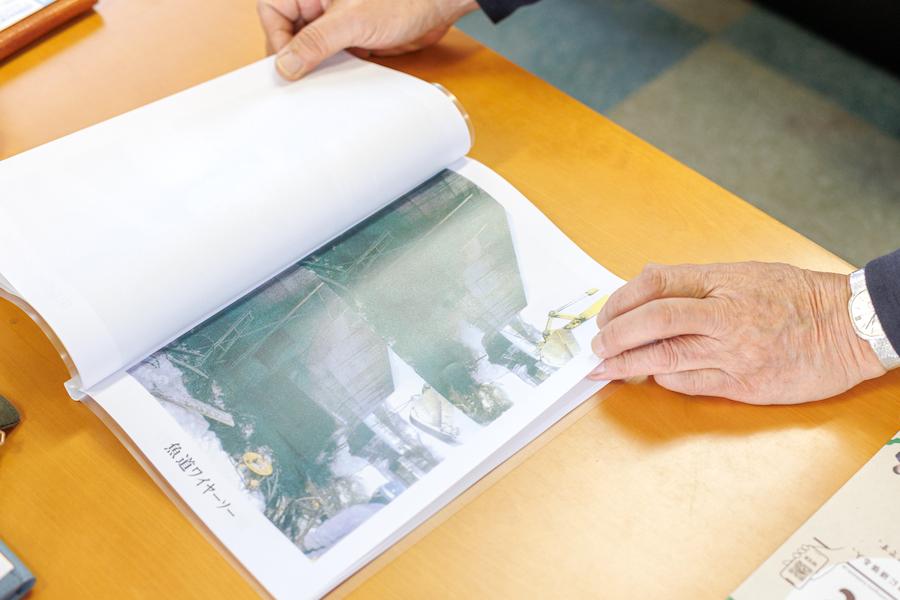
さらにアンカーのメーカーから、寒冷地・北海道での硬化や強度の試験をしたいので協力してほしいという依頼も寄せられるそう。長年、この業界で仕事をして実績を積み重ねてきた小宮社長の人脈と信頼があるからこそのエピソードです。
信頼を得るために必死に勉強。技術や知見、人脈のバトンを次世代へ繋ぎたい
さて次に小宮社長が会社を興すきっかけ、会社の成り立ちについて伺っていこうと思います。
小宮社長が創業したのは平成元年(1989年)。会社を始める前は、帯広にある実家の小宮銃砲火薬店に勤務していたそう。
「僕はもともと札幌生まれなんですよ。小学校くらいまでいたかな。父親の実家が北海道大学のそばにある小宮銃砲火薬店で、分家することになってうちの父が帯広で同じ名前の小宮銃砲火薬店を開いたんです。ちょうど昭和35年くらいだったかな」
男3人兄弟の真ん中だった小宮社長は、工業高校の機械科を出たあと実家の店に入ります。この時点では現在の建設業に結び付く話が出てきませんが、こちらの疑問に気付いた小宮社長は「銃砲店からどうして建設業に?って思っているでしょ」とニッコリ。

「今は少なくなったけれど、昔は火薬の力を使ってコンクリートに穴をあける火薬式鋲うち銃というのがあったんです。うちはHILTI(ヒルティ)という建設業の工具メーカーと火薬の取引をしていて、メーカーの方といろいろやり取りをする中で、アンカーの仕事をやりませんかと声をかけられたのがきっかけだったんですよ」
建設業はまったくの畑違いの仕事ではありましたが、30代半ばだった小宮社長は思い切ってチャレンジしてみようと考えます。父親に独立したいと話すと、「いつになったら独り立ちするのかと思っていたよと言われてね」と笑います。ちなみに銃砲店はお兄さんが跡を継いでいるそうです。
メーカーのサポートもありましたが、手探りでのスタート。自ら建設現場の元請会社に営業回りをし、仕事を獲得するという日々だったそう。アンカー施工に関しては、ほぼ独学で技術も知識も習得していったと振り返ります。
「勉強はとにかく一生懸命やりましたね。でも、苦ではなかったですよ。仕事ってね、最終的には人対人だと僕は思うんです。小宮さんに任せたら安心って言ってもらえることが何より大事だと思っていたから、取引先の方たちに信頼してもらえるようにきちんとした仕事をしようと思って、必死で勉強しましたね」

真摯な姿勢と丁寧な仕事ぶりが評価され、仕事を任される機会が増えていった小宮社長。さらに協会の役員などを頼まれるようにもなったと言います。
そうして創業から35年以上経ち、今の目下の課題は「人手不足と人材育成」と話します。「現場で活躍してくれるスタッフを育てていかなければと考えています。僕もいつまでも現役でいられるわけではないから、次の世代にバトンを渡さなければとも思っているので」と続けます。たくさんの人たちの暮らしや社会生活を支えるインフラ整備に関する仕事だからこそ、途絶えさせるわけにいかないと小宮社長。「僕がこれまで身につけてきた技術や知識、人脈もすべて次を担ってくれる人に継承したいと思っています」と語ります。
従業員たちが語る、厳しさもあるけれどアットホームで居心地のよい会社
次にバトンを渡すため、小宮社長が現場の工事に関する技術や知見を少しずつ引き継いでいるというのが、工事課長を務めている東口真光さんです。2007年から小宮工業に勤務しています。
 有限会社小宮工業で工事課長を務める東口真光さん
有限会社小宮工業で工事課長を務める東口真光さん
「ここに来る前も鉄筋業など建築業界にはいたんですけど、ちょうど29歳のとき、もうちょっとしっかり地に足をつけて仕事をしたほうがいいかなと思っていて、知人の伝手で小宮工業を紹介されたのが入社のきっかけです」
あと施工アンカーについては何も知らなかったという東口さん。最初のうちは先輩に付いていき、現場で少しずつ仕事を覚えていったと言います。
「もともとこの業界にいたので、現場にも割とスッと入ることができたという感じでした。あと、うちの会社はみんな仲が良くて、最初からなじみやすい雰囲気もあったんですよね」
仕事を少しずつ覚えはじめ、できることが増えると仕事自体が面白くなってきたと話します。「ここまでなんとなく続けてきたという感じなんですけど、仕事も会社の雰囲気も自分にはちょうどいいなと思っています」と続けます。

「どこの業界も会社も人手不足だと思いますが、うちも若手が入ってくれたらうれしいなと思います。新しい人が入ってきたら立場的に自分が指導をすることになると思いますが、未経験でも一人前になるまではとことん面倒見ますよ!もちろん建設現場は安全第一なので、ときには厳しいことを言うシーンがあるかもしれませんが、絶対に突き放したりはしません!」
そう力強く話す東口さんのもとで、現在仕事を教えてもらっているのが、半年前に入社した世良駿人さんです。世良さんは、「自分がてきぱき動けなくて現場で注意されることもありますけど、先輩たちはとにかくいっぱいかまってくれます」と笑います。
 穏やかな物腰が印象的な世良駿人さん
穏やかな物腰が印象的な世良駿人さん
実は世良さん、10年ほど前に小宮工業に一時期在籍していましたが、1年ほどで退職し、そのあとは電器メーカーの工場で機械オペレーターの仕事に従事していました。しかし、小宮工業を辞めたあとも東口さんとは繋がりを持っていたそう。
「実は、彼は僕の先生なんですよ」と東口さん。もともと大学で機械システムなどを学んでいた理系出身の世良さんは難しい計算式などが得意だったこともあり、東口さんがあと施工アンカーの施工士の資格試験を受ける際、解き方をレクチャーしたそう。その甲斐あって無事合格した東口さんは「教え方がうまいんですよ」とニッコリ。
その後、人手が足りないから戻ってこないかと東口さんが世良さんに声をかけたのがきっかけで再び小宮工業へ。

「戻って半年。いろいろな現場があるし、仕事が多岐に渡っているので、大変なところもありますが、1日1回は何かしら達成感を得られる仕事だなと感じています。僕自身はまだまだ覚えなければならないこともたくさんあるし、気を付けなければならないこともたくさんありますが、とにかく何かひとつでも一人でできるようになりたいですね」
東口さんと世良さんが話している様子をずっと笑顔で見ているのが、25年以上勤務しているベテランの山川義幸さんです。以前は料理人でしたが、日曜に休める仕事がいいのではないかと奥さんから勧められて入社をしたそう。
「まったくの未経験でしたけれど、仕事を覚え始めたらだんだん面白くなっていって、そのうち会社の業務の幅も広がっていったもんだから、飽きることなくここまで仕事を続けることができました。会社の居心地もよかったしね」
 こちらがベテラン職人の山川義幸さん
こちらがベテラン職人の山川義幸さん
実は山川さん、元請会社から個人で表彰されたこともある人物。現場での気配りや仕事の正確さなどが評価されたそうです。小宮社長からも絶大な信頼を得ている山川さんですが、体調のこともありこの春で一旦退職。無理のない範囲で、小宮工業で仕事を続けるそう。
「正社員じゃなくなるだけなので、新しい人が入ったら自分もお世話はしますよ(笑)。うちの会社は本当にアットホームで、社員同士の距離感がちょうどいいんですよね。新人さんが入ったら自分もマサ(東口さん)もグイグイ声をかけていくので、すぐになじめると思います。仕事を面白いと思えるまで少し時間はかかるかもしれないけど、そこまで一生懸命頑張れたら、大きなやりがいも感じられるようになるんじゃないかな」
山川さんは現場を任され、自分の采配で仕事ができるようになってから、さらにやりがいを感じるようになったそう。「無事に1日の仕事が終わったら、その日の夜はおいしいお酒が飲めるんですよ」と笑います。
インタビュー終了後はみんなそろって撮影。その際も皆さんリアンちゃんを交互に抱っこしたり、互いに冗談を言い合ったり、仲の良さが伝わってきます。
小宮社長が最後に、「うちの作業は表に見えない部分の仕事だけれど、インフラ整備は立派な社会貢献であるという誇りを持って、みんなには仕事にあたってほしいと思います」と話していたのが印象的でした。




















