
北海道の中心部に位置する、美瑛町。四季彩の丘や青い池を一目見ようと多くの人が訪れるこのまちの観光ルートから少し外れた五稜(ごりょう)地区に、廃校となった小学校の建物を活用した「AntaaLab(アンタラボ)」というインテリアショップがあります。建物の中に入ると、学校らしい天井の高い空間にたくさんの古い家具や雑貨などがびっしりと並んでいます。インテリアや雑貨が好きな人、アンティークなど古いもの、古道具が好きな人にはたまらない場所です。ついつい取材を忘れ、見入ってしまいます。今回はこのAntaaLabを運営する「デザイントーク有限会社」の代表取締役・大谷薫さんに、AntaaLabが誕生した経緯やこれからのことなどを伺いました。
 店内は北海道内の古道具や古材でいっぱい。その傷や形から昔の人の暮らしや歴史を考えるとワクワクします
店内は北海道内の古道具や古材でいっぱい。その傷や形から昔の人の暮らしや歴史を考えるとワクワクします
創造すること、デザインすることの楽しさに目覚めた大学時代
AntaaLabの話に入る前に、まずはここを立ち上げた大谷さんのことから...。
大谷さんは生まれも育ちも旭川。子どものころから、考えて作ること、「創造」することが好きだったそう。「父親が建築の仕事をしていて、遠からずその影響もあるかもしれませんね」と話します。
 二級建築士から宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、キッチンスペシャリストなどたくさんの資格をお持ちの大谷さん
二級建築士から宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、キッチンスペシャリストなどたくさんの資格をお持ちの大谷さん
「ただ、建築のほうには進まず、デザインに興味があったので、当時旭川にあった北海道東海大学の芸術工学部に進み、デザインを学びました」
今でこそ、「デザイン」というものは私たちの暮らしと密接に繋がっていると分かりますが、大谷さんが大学で学び始めたころは、「デザインは日常的なものではなく、特別なものと認識されることが多く、つかみどころのない感じでした。それで、デザインって何だろう?という興味からデザインを専攻した感じでしたね」と振り返ります。
大学で学びを深めるにつれ、デザインすること、創造することの楽しさに目覚め、在学中にデザイン関連の道に進もうと決意。周りからは「デザインの仕事って何?」と聞かれるような時代でしたが、中でもインテリアの分野に興味があった大谷さんは、大学卒業後、北海道発の大手家具・インテリア用品販売会社に入社します。

「まだ会社が上場する前で、平均年齢も27歳という若い会社でした。ここで、今の仕事にもつながるインテリアコーディネートの基本を学び、約11年勤務。アメリカ視察など、いろいろなことを経験させてもらいました」
建築現場で目の当たりにした、廃棄の山
その後、退職した大谷さんはもう一度インテリアデザインをしっかり学びたいと、母校の大学院へ進みます。2年間の院生生活を送る中、2人のお子さんを出産。子育てをしながら、大学院へ通いました。
「大学院を出たら、キャリアができると思っていたのですが、実際のところ就職先はなかなかなくて...。派遣社員としてシステムトイレなどの水周り製品でトップシェアを誇る企業の旭川営業所へ。その際、当時の所長が『コーディネート業で独立すれば?』と背中を押してくれて、起業することにしました。所長が覚えているか分からないけれど(笑)」

それがちょうど今から20年前。大谷さんは旭川でインテリアコーディネートを手がける「デザイントーク有限会社」を立ち上げます。
「いつか独立してやってみたいという気持ちはありました。もしこの仕事が世の中に求められていなければ会社はつぶれるだろうし、そのときはそのときだと考えていました」
今でこそ、インテリアコーディネーターを抱える建築会社も増えましたが、当時はまだ少なく、大谷さんはいろいろな建築会社からの依頼で、住宅や施設などのインテリアコーディネートを手がけるようになります。

さらに、二級建築士の資格を持っていた大谷さんは建設業の登録をし、設計から携わる案件も担うようになります。元請けとしてリフォームも手掛けるようになりますが、現場で目にして驚いたのは、まだ使えるのに廃棄されるものがあまりにも多いことでした。「壊して作る」という建築の現場には、トラック何台分もの廃棄物が出ることもあり、「なぜ、こんなに廃棄するものが出るのだろう」と大谷さんは疑問を抱くようになります。
北欧の人たちの暮らしを見て感じた、豊かな暮らし
また、2011年から5年ほど、終の住処について考えたいと、福祉の先進国である北欧を訪れていた大谷さん。毎年のようにフィンランド、デンマーク、オランダなどの高齢者施設や住宅を見学し、北欧の人たちの暮らしを見てきました。
「本当に必要なモノしか周りに置いていなくて、びっくりしました。でも、その空間はセンスがよく、美しく、機能的。とても豊かな感じがしました。北欧の人たちは、住まいの環境づくりに力を入れていて、優先順位が衣食住ではなく、住食衣なのです。そんな暮らしを私もインテリアコーディネーターとしてお客さまに提案していけたらと考えるようになりました」

そのころ、日本では断捨離がブームに。それまでは、どう美しく収納するかが重視されていましたが、断捨離という言葉が登場すると、みんながモノを捨てるようになります。
「整理収納アドバイザーの資格を取ったので、片付けの活動もはじめていました。確かにいらないものをどんどん捨てることで、必要なモノにだけ囲まれる暮らしの土台はできますが、たくさんのゴミを見て、最初はいいことをしたつもりでしたが、北欧で見て感じたものと何か根本が違う...、本当に豊かな暮らしとは何だろうと考えるようになりました」
古材や古道具に新しい価値を
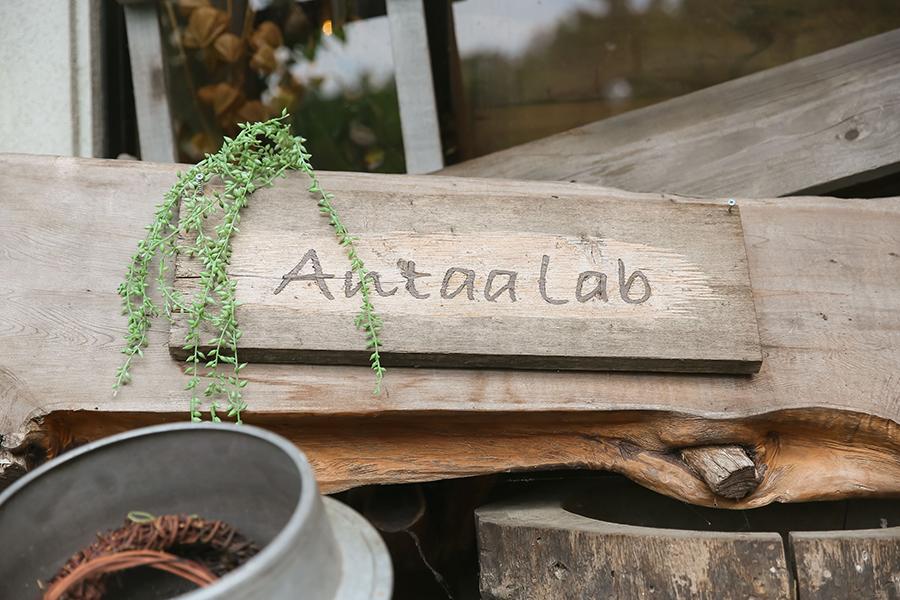
建築現場で廃棄されていくものを生かせないのだろうか。そして、もっとモノを大事にすることはできないだろうか。現状を理不尽に感じていた大谷さんは、内装業協会の人にその想いを話します。すると、その方から長野県にある「リビルディングセンタージャパン」(リビセン)を紹介されます。そこは、家や建物の解体で出た古材や古物を販売するリサイクルショップ。役目を終えたものを資源として再び利用し、古材を用いた空間デザインやオーダー家具も手掛けていました。大谷さんが理想と思う形に近いものを実践している会社でした。
「リビセンと出合ったのは、ちょうど2017年、2018年くらいでしたね。北海道でも同じようなことができないかと考え、すぐに構想を練り始めました。ちょうどコロナ禍に入ってしまったのですが、その間、じっくり考えることができました」

まず、廃棄される古材や古物などを保管するために大きな倉庫が必要でした。旭川や近郊エリアで倉庫を探していると、美瑛で廃校になった学校の建物があるという情報が入ってきました。3つの小学校が空いている状態だと聞き、大谷さんは外側から建物を見にいきます。
「ちょうどいいサイズだったのが、この五稜小学校でした。それで、まずは管理している町にプレゼンをしようと、企画書を書いて提出し、なんとか貸していただけることに。2022年、無事オープンすることができました」
 AntaaLabの拠点として再び息吹が吹き込まれた五稜小学校
AntaaLabの拠点として再び息吹が吹き込まれた五稜小学校
Antaa=循環。「もったいない」の思いをつなげる
店名の「Antaa」とは、フィンランド語で「循環」という意味。大谷さんは、「循環」をこの店で示していきたいと考えます。
「フィンランドをはじめ、北欧の国ではモノを大切にする文化が根づいています。日本でも昔は『もったいない』という感覚や文化がありましたが、使わずにためこんでいるものも...。私たちは、住宅や店舗、解体現場などから、世の中に循環させられるモノを引き取り、それらに新たな価値を見出し、次の使い手に渡していきます。ここは、そんな捨てない暮らし、循環させる暮らしを提案していく場所なのです」
AntaaLabをオープンする際、大谷さんも想定外だったのが、古材よりも古い食器や生活用品、古道具を引き取ってほしいという依頼でした。依頼者たちの「もったいない」という気持ちを大事にしたいと引き取っているうちに、「この通り、モノでいっぱいになってしまいました」と大谷さんは笑います。

ここでは、「もったいない」という気持ちを「救いたい」、循環できるモノを捨てずに「救いたい」という思いから、古材や古道具を引き取ることを「レスキュー」と呼んでいます。ただし、何でも買い取るリサイクルショップとは異なり、「次世代に残したいと思えるか」「次の使い方や活用方法を提案できるか」といった「循環」につながる基準をきちんと設け、レスキューしています。「若い人たちに負の遺産として残すようでは、循環とは言えませんから」と大谷さん。
オリジナルリメイク家具も古い家具の修理も
オープンから2年経ち、当初予定していたリメイク家具など、大谷さんたちのアイデアやデザインを生かしたものを少しずつ出すことができるようになったと言います。

6月には「捨てない暮らしのものづくり展」を旭川のギャラリーで開催。古い桐ダンスをシンクの下に取り付けたキッチンや、古いタンスに脚をつけたテレビボード、床の間の天袋を組み合わせた洗面台などが会場で披露されました。AntaaLabによって新たな価値を引き出されたこれらは、会場に訪れた人たちにも好評だったそう。「中には美瑛まで足を運べなかったから旭川で展示会を開いてくれてうれしかったという方や、展示会で初めてAntaaLabを知ったという方もいらっしゃったので、これからもこのような展示会を行っていきたい」と大谷さん。
 水周り製品を扱う企業での経験がある大谷さんだからこそのアイデア!
水周り製品を扱う企業での経験がある大谷さんだからこそのアイデア!
こうしたリメイク家具やリメイクキッチンなどは、もちろん美瑛のAntaaLabでも見ることができます。「少しずつですが、自分たちがデザインしたリメイクものも増やしていきたいですね。ここは捨てない暮らしを提案するショールームでもありますから」と話します。つい、古道具や食器に目がいってしまいがちですが、AntaaLabを訪れたら床などもチェックを。いろいろな種類の木板がパッチワークのように貼り付けられています。これらは捨てられるはずだった端材を使用。このような使い方ができるという提案も兼ねており、まさにショールームです。
工房になっている体育館を拝見すると、各所から引き取った古い建具や古材がびっしり。職人の方がこれらを循環させるために製作にあたっています。

「建具などは、現代の住宅のサイズに合わないものもあるので、それをうまくリサイズしてドアにしたり、パーテーションを作ったりして循環させるように工夫しています。古材はリフォームする際に古いものを使いたいという方がいれば、販売もしています」
工房では古い家具やイスの修繕なども対応。「思い出のものなので長く使いたいという方も多くいらっしゃいます」と話します。中には、元のような使い方はできないが、思い入れがあるので、何か別の形にリメイクできないかという相談もあるそう。「大事にしたいという気持ちを私たちも何とかしたいと思うので、気持ちに寄り添った提案をさせていただいています」と続けます。

心とつながるインテリアで、丁寧な暮らしのきっかけ作りを
これからやっていきたいことや目指しているところを伺うと、「古い家をトータルでリメイクしてみたいですね」と大谷さん。リフォーム工事の際、AntaaLabの古材や古いものをアレンジして使ったケースはあるそうですが、まるごとフルでリメイクしたことはないため、「ぜひ挑戦してみたい」と話します。これは町内の空き家活用に役立つかもしれないとも続けます。
また、移住者の人たちが循環の考え方に興味を示してくれているそうで、移住者はもちろん、町の人たちとつながり、循環の輪を広げていけたらとも考えています。

「私たちの活動をもっと広く知ってもらいたいので、若い人にも関わってもらい、活動内容を拡散していきたいですね。今、学生のインターンを受け付けているのですが、インターンを検討してくださる方には、楽しく一緒にモノを使い切ることについて考えたいと思います。AntaaLabに来て、モノとの向き合い方、『丁寧に暮らす』ためのヒントや気づきを得てもらえたらと思います」
「カーテンを変えるだけで心が晴れやかになるなど、インテリアは心の動きと連動している」と大谷さん。「捨てない暮らしの先にあるもの」を見据えながら、美しさと楽しさを感じられるインテリアコーディネートをこれからも提案していってくれるのでしょう。


- AntaaLab(アンタラボ)
デザイントーク有限会社 - 住所
北海道上川郡美瑛町五稜第5
- 電話
0166-74-5552
営業時間/10:00〜17:00
定休日/火曜・水曜
アクセス/車でお越しの際は、ナビに「五稜小学校」と検索、またはGoogleマップでAntaa labと検索していただくと便利です
















