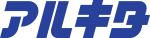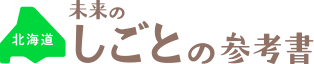JR追分駅前にある「追分ホテルわたなべ」は、宿泊・飲食・仕出しを行う、まちになくてはならない存在です。餅を売る屋台から事業をはじめ、戦後に割烹旅館だった建物を買い取って現在の礎をつくった初代と2代目。現社長である3代目の渡辺隆広さんは、一度はサラリーマンになったものの、安平町に戻って後を継ぎました。鉄道のまちと歩んできたホテルの歴史、そして家族のストーリーを伺います。
和洋中から職人が握る寿司まで、食事も愛されるホテル

新千歳空港から車で30分、札幌からも1時間ほどの場所にある安平町。かつて鉄道の町として栄えた追分駅のすぐ目の前にあるのが「追分ホテルわたなべ」です。この地を訪れる客を長年受け入れてきた宿であり、宿泊客以外も利用できる「レストラン渡辺」と「江戸前 栄寿司」も備えています。
レストランでは和洋中から寿司まで豊富なメニューを提供。特製デミグラスソースの「とろとろオムライス」やブランド豚を使った「とんかつ定食」、職人が握る寿司とサクサク衣の天ぷらが両方楽しめる「寿司そば天セット」、気軽に食べられるラーメンも人気だとか。仕出しも行っているので、まちでは「何かあればわたなべさん」と頼られる存在。道の駅でイベントがあると、それに合わせたお弁当もつくります。鉄道にちなんだイベントも多く、11月に行われた鉄道模型フェスでは、大正時代の味と包装を復刻した駅弁を販売、あっという間に売り切れたといいます。
「復刻駅弁は、大正生まれのおばに当時の味を聞いたり、自分が子どものころに食べた母親の弁当の味を思い出したりして中身を考えました。昔のものを正確に再現したわけではないけれど、懐かしい雰囲気を感じさせる味にしましたね」と、渡辺社長。ふたを開けるとSLの形に見える助六弁当を提供したこともあります。太巻きを車輪に、こんぶ巻きを煙突に見立てるなど工夫を凝らしたのだとか。
「売り方も凝っていますよ。道の駅の責任者と一緒にイベント弁当の企画をするんですが、昔の駅弁売りの実演をする方を呼んで『弁当~、弁当~』って言いながら売ってもらうんです。みなさん、とても喜んでくださいます」
列車の乗客に餅を売る屋台から旅館・飲食店を営むように
3代目の渡辺社長に、ホテルわたなべの歴史をお聞きしてみました。時代は昭和初期にさかのぼります。
商売を始めたのは渡辺アキさん、渡辺社長の祖母に当たります。当時の追分駅は、夕張や三笠からの石炭列車を引っ張るSLの燃料や水の補給を行う重要な駅でした。駅の売店や車内販売はない時代。列車の乗客は駅前にずらりと並ぶあめや駄菓子の屋台で買い物をすることが多かったのです。そのなかのひとつ、餅をこねて売っていたのがアキさんの屋台でした。昭和15年ごろから終戦までの5年間ぐらいのことです。
会社勤めをしていた夫は商売に関わらなかったのですが、息子は中学生のころから登校前に餅をつき、それを祖母とおばがこねて丸めて売り物にしていました。屋台の向かいには割烹旅館があり、陸軍や運送会社のお偉いさんたちが食事をしたり宴会をしたりと、それはにぎやかだったそうです。
戦後しばらくして、割烹旅館の建物は売りに出されました。これを好機と捉えて、建物の一部を切り売りしてもらい、3回に分けてすべて買い取ります。この建物を使って、最初は食堂、続いて旅館、寿司店と喫茶店とBARも始めました。この頃、経営はアキさんの息子夫婦、つまり渡辺社長のご両親に代替わりしていました。
寿司店を併設した理由を渡辺社長にたずねると、
「買い取った建物の階段下スペースが空いていたので、そこにカウンターを設けて寿司屋をやろうと思ったらしいんですね。父は寿司職人を見つけるのも徹底していて、ある寿司店の名店にしばらく通い続けて、マスターと懇意になってお互いに信頼が置けるようになってから、『この人なら間違いない』と、若手の有望な職人を紹介してもらったそうです」
そのころ、追分駅には国鉄の機関区、保線区、車掌区があり、まちで暮らす人の約半数が鉄道関係で占められていました。
「映画館にボーリング場、飲み屋も20軒ぐらいあって、ものすごくにぎわっていました。その流れで、食堂の2階に喫茶店とBARをつくったこともあるそうです。ものすごく繁盛していたみたいですね」
働く母親の背中を見つめ続けてきた3代目渡辺社長

渡辺社長は上に姉が2人いる末っ子として生まれました。小学生のころは暗くなるまで思い切り外で遊び、中学から高校までは陸上部で中距離走に熱中します。「勉強は苦手でしたけれど、ずっと全力で長い距離を走れる中距離が楽しかったんですよね」と渡辺社長。料理が好きで、調理師の專門学校へ行きたいと思っていましたが、父親から「これからはコンピューターの時代だ」と言われ、札幌にあるコンピューター関係の專門学校へ進んだそうです。
「当時は、まだパソコンというよりもワープロの時代でしたが、商工会長だった父親はさまざまな人との交流を通じて新しい情報を得ていました。それに、調理師免許を取るなら、学校に行かなくてもうちで経験を積んで試験を受ければよいわけで、そう言われればそうかな、と」
2代目の両親は、長男である渡辺社長に後を継ぐことを期待されていたのではないでしょうか。
「継ぐとか、継がないといったことは言われませんでしたね」と渡辺社長。
後継者にと言われなかったのには、母親の苦労もあったようです。
「父は調理もしていましたが、追分町の議長や商工会長、消防団副団長など多忙でしたので、実務のすべては母が担っていました。旅館の朝食から始まり、食堂の昼営業と出前、客室清掃、宴会料理の準備と旅館の夕食。深夜までBARのチーママ。そして3人の子育て。ものすごく苦労したのではと思います」
息子に自分のような苦労をさせたくない。渡辺社長のお母さんはそう思っていたのかもしれません。
炭鉱のまちで生まれ、小学校しか出なかったという母親は「つらい思いをした分だけ、それを倍にして周囲に優しくするような人」だったとか。社長の妻である佳枝さんはこう話します。
「お姑さんは、とにかくまちの人たちから慕われていましたね。私が社長と結婚するときも『ママは良い人だよ』と口々に言われましたし、結婚してからも嫁である私を守ってくれて、何の心配も要りませんでした」
「うちの仕事が性に合っていた」地元に戻って得た実感
札幌でコンピューター関係の専門学校に入った渡辺社長は、喫茶店の調理や結婚式場のスタッフ、居酒屋の店員などのアルバイトに励みます。
「母親のやっていることが、自分にとっては『仕事』だと思っていたのか、調理や接客関係ばかり選んでいました」
専門学校を卒業した後は、食品会社に営業・販売職として就職しました。しかし、毎日の睡眠時間は3時間。起きてから眠るまでが仕事という生活を続けるうちに、心身がボロボロになってしまいます。あるとき、尋常でない様子を見た父親の「家で休みながら仕事を手伝えばいい」という言葉で、実家に戻ることになりました。
渡辺社長は、実家のホテルで調理補助や接客スタッフとして働くようになります。
「やはり料理が好きだったんですよね。調理場で練習して玉子焼きが焼けるようになり、試食してもらったら『うちで一番上手だから、今度からは頼むわ』と言われて。それから、少しずついろいろな調理を任されるようになりました」
コンピューターの知識や資格を生かして、書類作成や発注関係など経営的な業務も行うようになります。母親との共同経営だった期間を経て、2010年に3代目社長になりました。
愛のある、温かい接客を受け継ぐ渡辺ファミリー
宿泊部門を担当している奥さまの佳枝さんにも、お話を聞いてみましょう。佳枝さんは滝川市出身で、函館の看護学校を卒業後、札幌の病院で働いていました。渡辺社長とはキャンプで知り合ったのをきっかけに結婚します。多忙な宿泊・飲食業を営む渡辺家へ嫁ぐことに、不安はなかったのでしょうか。そう尋ねると、「いいえ、私は結婚した後も仕事をしたかったんです」と、言葉をこう続けます。
「ずっと看護師の仕事を続けてきましたし、働くのが好きなんですよ。先ほどお話ししたように、お姑さんはとても良い人でしたしね。長女を産んだときは、休憩所にベビーベッドを置いて面倒を見ながら働いていましたが、パートさんたちがよく娘をあやしてくれました」

佳枝さんの隣で、娘のきみかさんが少し照れたように笑います。お母さんと同じように朗らかで明るく、取材中もさりげない心配りを見せてくれたきみかさん。保育園の先生が大好きで、ふたりの妹の面倒をよくみていたことから保育士になりたかったそうですが、高3のときにいとこの話を聞いて管理栄養士を目指すことに。進路を変えた理由については、こう話します。
「高校生のときも調理の手伝いをしていたので、私にとって食べ物を扱うのは身近なことでしたし、祖父が病気になったこともあって、食事と栄養の知識を学んで役立てたいと考えました」
きみかさんは、いとこも学んだ管理栄養士コースがある江別市の酪農学園大学に進みます。サークル活動ではメンバーが百人以上所属するYOSAKOIサークル「祭」に所属。踊り子やスタッフとして、楽しく充実した日々を送りました。
卒業後は、管理栄養士として東京に本社のある企業に就職、入社式では新入社員代表のあいさつも務めました。道内の施設に配属されたきみかさんでしたが、引き継ぎがないまま前任者が異動してしまいます。手探りの状態でさまざまな業務をこなさなければならず、朝4時半から夕方までずっと緊張しながら働きづめの日々。作業中に涙をこぼすこともあり、疲労は限界に達していました。
渡辺社長は、かつて自分が父親に言われたように娘に言います。
「辞めてもいいんじゃない?休みながらうちで仕事をしてもいいよ」
きみかさんは、現在はレストランで調理やホールを手伝っています。
「慣れ親しんだ場所で、安心して働いています。ここのみんなはとても優しいんですよね」と話すきみかさん。すると、「お父さんは厳しいよね?」と聞く渡辺社長。「そうなんですよ!私が頑張ってネギを切っているときに『ネギはまだか?』って言ってくるんですよ?」と、親子らしい会話に笑みがこぼれました。
両親と祖父母を尊敬しているというきみかさん。特に、祖母はすごい人だったと語ります。
「2代目だったおばあちゃんは、とても温かい接客をする人でした。まちの人たちからもすごく愛されていたんですよね。だから、私も、笑顔で温かい対応をするようにしています。時々、お客さんから私が母や祖母に似ているって言われると、とってもうれしいですね」
もしかしたら、娘さんが4代目になるのでは...?と期待されそうですが、渡辺社長は「継がせることは考えていません」ときっぱり。あくまで、次の職場へ行くまでのアルバイトとして雇っているそうです。きみかさんも「そのうち、管理栄養士として復帰したいと思っています!」と晴れやかに話してくれました。
震度6強の地震が発生、避難所への炊き出しに奮闘!
コロナ渦の数年は、ホテルわたなべにとっても厳しい時期だったのではないでしょうか。そうたずねると、渡辺社長からは「コロナだった時よりも、あのころがもっときつかったですね」という答えが。
「あのころ」とは、2018年秋に発生した北海道胆振東部地震です。安平町では最大震度6強を記録し、甚大な被害がありました。ホテルわたなべの建物にも壁に亀裂が入り、3階にあったボイラーが破損して階下は水浸しになったそうです。
深刻な状況のなか、渡辺社長がまず考えたのは、炊き出しをすることでした。
「停電が続くと冷蔵庫や冷凍庫にあるものは腐ってしまうから、炊き出しで使ってしまおうと思いました。幸いにも隣がガス屋さんで、真っ先に復旧させてくれたんですね。ですから、最初に出したのはメンチカツだったかな...、揚げ物やそうざいをつくって炊き出しを行いました」
日数がたつと、炊き出しに来てくれるボランティアが増えてきます。しかし、そこで気づいたことがありました。
「みなさん、それぞれに都合がありますから、3日間だけ、夕食だけといった炊き出しになるんです。そうなると、炊き出しのないときは食事がカップ麺や乾パンだけになってしまうんですね。幸いなことに、うちのホテルは電気も水道も早く復旧しましたから、朝いちばんに避難所に行って、避難所の指揮を取っていた町職員と3食の打ち合わせをしました。朝食がパンだけの場合には、温かいみそ汁をつくって持っていくといったふうに、足りないメニューを補っていったんです」
渡辺社長は、町外からのボランティアの人たちの食事についても気になっていました。ボランティアは原則として被災者向けの食事をもらうことができません。しかし、この近辺で開いている飲食店やお弁当屋さんはありませんでした。
「冬の寒い季節に入っても、彼らは持参した冷たいおにぎりをかじるだけで活動している。少しでも早くレストランを再開して、温かいものを提供できるようにと頑張りました」
駅前だからこそ、ホテルの明かりを灯し続ける

避難所の運営や、地震後の復旧作業には、たくさんの人たちとの協働が欠かせません。この災害によって、渡辺社長は、人とのつながりの大切さをいっそう強く感じるようになったと言います。
翌年の春には「道の駅 あびら D51ステーション」が追分地区にオープン、多くのお客さんが訪れるようになりました。道の駅の責任者は、避難所の指揮を取っていた町の職員です。
「彼は、道の駅だけでなく、まち全体のにぎわいをつくろうと真剣に頑張っている人です。だから私も、一緒に協力していきたいと思っています」
このホテルを、そして自分たちを育ててくれた我がまちに、少しでも恩返しをしたい。
「ホテルの修理にかなりお金がかかりましたが『ここがなくなったら困る』と言ってくれるお客さんたちが少なからずいらっしゃる。こういったつながりがあるからこそ、踏ん張ってもやっていきたい、そう思っています」
今日も、JR追分駅の前には、ホテルわたなべの明かりが灯っています。